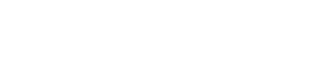-

『Lady Grey』着想はアントナン・カレームの古いレシピ。
48時間かけて低温で焼いたオレンジの中身をくり抜き、果肉、アーモンドのエスプーマ、紅茶のアイスクリームをNouri ヌーリ
文化の交差点、シンガポールにふさわしい
クロスカルチャー・キュイジーヌとは流行り廃りのあるテクニックではなく、人類の歴史の根元にある、人をつなぐ食にフォーカスしたいと考えたイヴァン・ブレム氏がオープンしたレストランが【Nouri】だ。足を踏み入れると、違和感を感じる人もいるかも知れない。それは、【Nouri】が他のレストランと異なっているからだ。間口からは想像もつかないほどの奥行きがあり、正面に目に飛び込んでくる巨大な細長いテーブルは相席スタイルの客席、その先は段差一つなくそのままオープンキッチンとなっており、食材を刻んだり、盛り付けをするスタッフの姿が見られる。食事をするゲスト同士のみならず、厨房スタッフとも「場所を分かち合う」理由は、「料理を通して、差別や偏見などを生み出す『境界』のない世界をこの場所から実現していきたい」という、イヴァン氏の思いからだ。
どの料理を頼んでも一番最初に出てくるのは自家製のサワードゥブレッドと、蒸し器のような『スティームジューサー』で、7種類ほどの野菜から抽出したエキスを使った優しい味のスープ、そして「絹ごし豆腐」と呼ぶ、柔らかなミルクのパンナコッタ。英語で「パンを割る」という言葉は、「食事をする」という意味以外に「分かち合う」という意味があり、それにかけた形だ。温かいスープは胃を温め、ホッと落ち着かせる効果があり、「絹ごし豆腐」も、誰もが赤ちゃんのときに初めて味わう、ミルクをイメージしたもので、「ミルクは店名の由来である『癒す』という意味に加え、純粋さ、無垢の象徴でもある」という意味で重要な要素。ヘストン・ブルメンタールの【The Fat Duck】では、イギリス王室図書館などを通して新しいレシピの研究開発を担当していたが、その際に気づいたのは、「イギリスの食文化の90%は実は海外からやってきたものだ」ということ。その時抱いた好奇心から、はるかに時代を遡るリサーチの旅が始まった。「文化は、世界各地での、異なった気候などの環境に適応するために、人間が考え出したもの。でも、文化に触れていない赤ちゃんが好きな味は、甘味や旨味。それは、国籍を問わず変わらない」という考えから、それぞれの文化の違いを尊重しながらも、その共通項を探っていくために、今年ラボを設立。人類学などを通して、世界に共通する味のバランスも研究している。ブラジル出身ながら、ドイツ、ロシア、イタリア、スペイン、シリア、レバノンと多様な血を受け継ぐイヴァン氏にとって、それは自らのアイデンティティとも繋がっている。シンガポールに根ざした味として、昔、この一帯がナツメグの産地だったことから、テーブルにはナツメグの実が飾られ、ディナーはナツメグの果肉の砂糖漬けで締めくくられる。多民族国家シンガポールで楽しむにふさわしい、多文化の共通項を提示する料理。それは、活力溢れるシンガポールの今の成功にも、どこか重なって見えた。-

『Break Bread』ミルクで作られた「絹ごし豆腐」(写真手前)の上には、ナツメグの果肉のピクルスが。ここから最後の小菓子のナツメグの果肉の砂糖漬けまで物語が繋がる -

『Scallop Ceviche』南米料理を代表するセビーチェだが、ポリネシアの人々が広めた説もあるとイヴァン氏。ホタテ、ポン酢、ココナッツミルクで国境を超えた味を表現する -

テーブルに着くと置かれているナツメグの実と、「あなたが癒すものが、あなたを癒す」と書かれたメッセージ

シェフの流儀 イヴァン・ブレム氏
「カレームはすでにオレンジの皮に詰めたデザートを木に吊るし、食事客に収穫させる「体験型」の料理を提供をしていた。歴史を知るにつれて、自分が『クリエイトした』と思っても、実はすでに歴史の中で使われていて、再発見されているに過ぎない」と感じるのだという。
-
世界の文化が交錯する国で
体験する新しい味
最新!
シンガポールで
行くべき
トップレストラン
Hitosara special
交易によって食材を調達し、食文化を独自に発展させてきた国シンガポール。
まだ若い国だからこそ、その進化のスピードは速く、エネルギッシュで刺激的だ。
『2019年アジアのベストレストラン』No.1に輝いた【オデット】のフランス人シェフをはじめ、
人気レストランの料理人の国籍が様々なのもこの国らしいところ。
アジアで随一のメルティングポット、シンガポールを今味わうなら、この5軒へ。
Photographs by Lin Minglong Desmond / Coordination&Text by Kyoko Nakayama / Design by form and craft Inc
※営業時間、定休日などの情報は変更されることもございますので、あらかじめご了承ください。