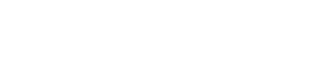信長のシェフ
戦国にタイムスリップした料理人・ケンが示す“時代に流されない生き様”
織田信長に認められた“記憶喪失の料理人”
織田信長――日本人なら誰もが知っているであろう、戦国三大武将のひとりですね。
教科書に載っているのは肖像画のみで、現代のように鮮明な写真は残されていません。実際の信長はどんな顔をしていたのか、みなさんは自分なりにイメージしてみたことはあるでしょうか?
今回ご紹介するのは『信長のシェフ』というマンガ。2013年から2年連続でドラマ化されていたので、ご存知の方も多いでしょう。
信長を演じていたのは、王子様キャラが板についている及川光博さん。あの切れ長の瞳を想像するだけで、信長はきっとハマり役だったのでは…と確信できそうですよね。
しかし、この作品の主人公は信長ではないのです。
ドラマではKis‐My‐Ft2の玉森裕太さん(これまた王子様キャラ!)が料理人のケンを演じており、彼こそが“信長のシェフ”なのです。
物語の幕開けは1568年の京都。
ケンは間者(現代でいうスパイ)と疑われ、刀を持った兵士たちに追われていたものの、川に飛び込んでなんとか命拾いします。その様子を見ていた鍛冶職人の夏に面倒を見てもらうことになるのですが、なんとケンの手には川で捕まえた“宇治丸”が…。
このケンという男、実は現代(平成)からタイムスリップしてきた身で、自分の正体にまつわる記憶をすっかり失っていました。平成で着ていたと思われる白いコックコート姿のまま走っていれば、戦国時代にしてみれば不審極まりなく、間者と見なされてしまっても仕方ありません(苦笑)。
さて、話が前後してしまいましたけれども、ケンの捕らえた“宇治丸”とはウナギの別名です。
なぜ宇治丸なのかというと、ウナギは戦国時代、京都の宇治川で取れる魚だったから。夏がウナギではなく宇治丸と呼んでいるのを聞き、ケンは「ここは…戦国時代の京都なのか…」と理解します。
…そう、ケンは不思議なことに、食べ物の知識と料理の技術だけはハッキリと覚えているのでした。
宇治丸を料理しようとした夏に対し、「俺がやります」と待ったをかけるケン。みなさんはウナギ料理の定番といえば蒲焼きを思い浮かべるかもしれませんが、当時はまだ醤油さえも普及していなかったため、ケンは作るメニューを変更します。
そして調味料の制約をものともせず完成させたのが“宇治丸のネギ塩焼き 干し大根の味噌和え”。これを食べた夏は感動し、「きっとお前はどこかの城の料理人だったんだよ」とケンに伝えました。
4カ月後、夏の言葉は現実のものとなります。
自作の“鴨焼きまんじゅう”で商売をしていたケンの評判は、京都を訪れていた信長の耳にも届きました。信長はケンを岐阜城へと連れて行き、有無をいわさず新たな料理頭に任命。
まったくもう、スピード出世にも程がありますよね…!
“平成”の価値観は“戦国”の処世術たりうるのか
迷い込んだ戦国時代にて、料理人としての地位を着実に築いていくケン。当時の日本に存在しないはずの西洋料理を次々と披露し、多くの偉人たちを唸らせます。
例えば信長の正室・濃姫には“茹で海老蝶仕立て サバイヨンソース添え”や“あんパオン”(パオン=ポルトガル語でパンの意)を献上。ソースもパオンも濃姫にとっては未知の単語でしたが、味については「いとうまし」といわしめます。どことなくシュールではありませんか?(笑)
ただ、信長たちの普段の食事を担当するだけならまだしも、ときには大鍋を背負って戦地に赴かねばならないのです…。人々が血を流して争う光景を目の当たりにしたケンは、心を痛めずにはいられません。
平成の感覚をもってすれば当然、戦国時代で過ごす毎日は非日常に思えるでしょう。ケンは実際、信長に「斬れ」と命じられた相手を殺めることができないなど、戦国を生き延びる上での“甘さ”を何度も指摘されてしまいます。
このほかにも、過去にタイムスリップした人間が必ず直面するであろう悩みがありますね。
…それはすなわち、タイムパラドックス。
自分が未来から来たことを隠しているケンは、「俺が手を加える事で歴史が変わってしまったら…?」と、密かに葛藤するのです。
具体的なエピソードを挙げてみますと、作中では信長と明智光秀が2人で食事する場面があり、ここでもケンが料理を任せられました。
あの有名な「本能寺の変」が起こるとされる日付まではまだ10年以上ありましたが、ケンがどんなメニューを用意するか次第では、両者の距離を縮めることも遠ざけることも可能…。もはやケンの腕には、それだけの影響力が秘められていたんです。
ケンは結局、信長と光秀が一緒につつくことのできる“きりたんぽ鍋”を振る舞いました。そこにあったのは「俺のするべきことはその時のベストの料理をつくる、それだけだ」という覚悟。この料理人としてのプライドこそ、ケンが戦国を生き抜くための活力になっているのでしょう。
また、ケンはこんな風にも語っています。
「食べるということは、生きるということです。俺は料理人で…微弱ながらそれをお手伝いするもの。たとえ今がどんな時代であろうとも、相手が誰であろうとも、これだけは曲げられない!」
みなさんにも、曲げられない信念はあるでしょうか。
仕事、恋愛、趣味、お金…。何だって構いませんけれど、自分が自分であり続けるためには、どこかで筋を通していたいもの。
ケンのように過去へ戻ったとしても、逆に遥か先の未来へ飛んだとしても、大切なのは“今”を自分らしく生きることですよね。信長が気に入ったのは料理の味だけでなく、ケンのそういった姿勢もなのかもしれません。