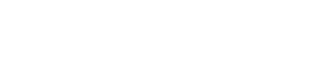国東という地で牡蠣を愛した男がつくった、どこにもない牡蠣

大分県の北東部、瀬戸内海に突き出した国東半島は、半島全体に火山群の峰々がそびえ、丘陵地と谷が放射状にのびる、日本の秘境百選にも数えられる土地だ。平安の昔から、天台寺院と宗徒による神仏習合の舞台として、最盛期の江戸後期には65もの寺と800を超える宿坊があったという。今も、峯入りなどの仏教文化が深く息づいている。
小城山展望公園の展望台に立てば、瀬戸内海をはさんで愛媛県から佐賀関媛までが見渡せる。六郷満山の石段を登り始めると、この地域独特の磨崖仏が姿を現す。苔むした風格のある姿に、畏敬の念を覚えずにはいられない。

さて、くにさきOYSTERは、そうした神々が宿る半島の北東部に位置するヤンマーマリンファームで作られている。それは、大分空港から10分ほどの場所に、海洋資源の研究のために30年前に建設された施設だ。農業機械の名門企業『ヤンマー』が、なぜ牡蠣?と不思議に思う人もあるだろう。実は、ヤンマーは小型船舶のエンジンでは世界のトップシェアを占めており、漁船つまり漁業とも深い関わりを持っているのである。長年、第一次産業をサポートするというこれまでのスタンスを、創業100年を機に、食材そのものの生産にも積極的に取り組んでいくべく路線を変更した。この5年、力を入れている牡蠣の養殖事業もその一環である。

マリンファームでは、以前から、あさり、牡蠣、とり貝などの二枚貝の幼生を育て、産地へ出荷するビジネスを行っており、北海道・厚岸で牡蠣養殖を成功させた加藤元一さんを研究者とし、牡蠣の養殖を始動させた。話が前後するが、加藤さんは、大学で水産学を学んだのち厚岸へ渡り、厚岸牡蠣を作るプロジェクトに参画した人物。その際の施設や設備をサポートしたのがヤンマーだったのである。
その縁で、ヤンマーへ移籍したのがちょうど12年前。当時、大分県では下降線をたどっていた水産業を回復するために、“捕る漁業から、育てる漁業へ”のスローガンをたてていた。車海老の養殖事業が打ち切りになった干潟で何かできないだろうかと、県がヤンマーに話を持ちかけたことが、くにさきOYSTERの誕生の始まりだ。
「そのときはきたー!と思いましたね。牡蠣を作らずに何をしろと、そんな気持ちで一も二もなく、牡蠣養殖に取り組むことを決意しました」と加藤さんは言う。

牡蠣の授精、幼生の餌、干潟での育成・・・・・・何から何までオリジナル
加藤さんが選んだ牡蠣は広島系のマガキだ。日本固有の純血種で、色が黒く、食味がいいのが特徴だ。瀬戸内海性気候の国東だから、広島種が適しているだろうという判断による。マリンファームでの牡蠣養殖は、研究所での幼生づくりと、育てた稚貝を海で育てる二段階に大きく分かれる。独自の手法で水質が管理された海水(後述)で満たされた水槽の中で雌雌を選別した貝を受精させ、幼生を生み出す。
クリーンな海水で幼生を育てるためには、えさとなるプランクトンが必要となるが、良質なプランクトンを作り出す技術こそが、ヤンマーが開発した最大の技術の一つである。濃縮された原液に光をあてて光合成を促し、プランクトンを量産する。
「海中での自然受精を待つ、これまでの日本の牡蠣養殖と異なり、陸上の研究所で受精させるヤンマーとの一番の違いは、すぐれた親同士を選べるということです。食味のよいもの同士、大きいもの同士、殻の深いもの同士などを掛け合わせて、より美味しく、消費者が望まむ牡蠣ができるのです。また、純血を保てるので、殻の色も真っ黒なんですね」と加藤さん。


幼生が小石大になったら、海へ。オーストラリアに特注した、三角柱の金属製のかごに100個ほどの牡蠣を入れ、干潟に移す。干潟というのはご存知の通り、潮が引いているときは砂地が現われるが、満ちてくればケースはすっかり海水につかってしまう。
通常の国産の牡蠣養殖は、ロープにホタテの貝柱をつるし、受精卵の多い海域に沈める。幼生は付着する性質を持っているため、ホタテの殻について成長を始めるからだ。しかし、くにさきOYSTERはすでに貝になった状態で海に戻すため、こうした独特の手法で生育が可能になった。
牡蠣は海中にいる間、二枚貝を開いて海の養分を摂取する。ところが、干潟では、殻をかたく閉じて水分蒸発を防ぐ。つまり、1日2回の殻を開閉することで、貝柱の筋肉が鍛えられ、歯応えのよい仕上がりとなるわけだ。

「ずっと海中につるしておく従来の方法のほうが成長が早いのでですが、ヤンマーでは、あえて干潟で育てています。そして稚貝の成長に合わせて、ケース内の密度を適正に保つために移し替えるんですね。大体2月に産卵・受精させ幼生を育て、5~8月は干潟で稚貝を育てる。9~10月はかごを沖合へ移して充分に栄養をとらせ、11月~12月に干潟で仕上げて出荷、というサイクルです」と加藤さんはこともなげに言うが、頭が下がる仕事量だ。こうして、通常の何倍もの手間と時間をかけて、収穫するまでの牡蠣が出来上がる。
牡蠣の水揚げ以降、出荷まで徹底される安全管理

ヤンマーマリンファームが牡蠣づくりにおいて、最も重視しているのが、安全性ということだ。牡蠣にあたる一番の原因はノロウィルス。しかしながら、牡蠣自身にはノロが発生する要因はない。なぜなら、ノロは人間と一部の霊長類にしか発症しないウィルスだから。にもかかわらず、牡蠣がノロを保有するというのは、生息する海域に、生活排水などからノロウィルスが入り込んでしまうか、もしくは保菌者が調理することによる以外にはありえない。やっかいなことに、ノロは大腸菌の1/500というサイズで熱にも強い。生活排水から完全に遠ざけることと、検査レベルを上げることでしか、排除することはできない。

そこでヤンマーでは、危険因子を排除した海水で幼生を育て、さらに汽水域からは遠い干潟で養殖する。定期的な海水の検査とともに、月曜日に収獲後、無作為抽出したサンプルを検査に出し、結果が出るまでマリンファーム内の水槽で待機させ、OKであれば、最終的に清流で24時間ろ過し、金曜に出荷。
こうして何重にも検査をすることで、危険因子を限りなくゼロに近づけている。検査の費用がかさむため、個人の生産者では、到底この規模の検査ができない。企業が本気で取り組んでいるからこその精度といえよう。4年間、35万個以上出荷し、牡蠣を起因とする食中毒事故は1件もないという結果がそれを物語っている。

写真/今清水隆宏 取材・文/小松宏子