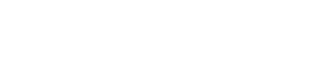猟をするようになったきっかけは“最高のおもてなし”をするため

幼少時から親戚のおじさんたちが獲ってきた鴨やキジを家で食べていたという小野寺さんは“ジビエは最高のごちそう”と話す。そんな彼は、社会人になるとクラシカルなフランス料理をつくる料理人を経験した。そこではジビエも扱っていたが、フランスではジビエが最高級の食材と認知されているのに対し、日本ではなぜ誰も見向きもせず、ジビエというとゲテモノに近い感覚を持っている人が多いのだろうと疑問を抱いた。昔から付き合いのあった猟師たちも、撃つことが最優先で食べることは二の次であった。これではいけないと、“本当のジビエの価値”を伝えるために「獲って、捌いて、調理して、食べる」ところまでが仕事の食猟師に転身した。彼は「自分の元を訪れる人たちには、天然の食材に触れてもらったり、その食材の料理を食べてもらったり、できる限り “最高のおもてなし”がしたいんです」と照れ臭そうに微笑む。

そのような活動をしてからしばらくした後、東日本大震災がきっかけとなりニホンジカの解体処理をはじめとした鹿肉や鴨肉の卸販売、アウトドア料理の指導や自然との関わり方や食育に関するワークショップなどを行う【Antler Crafts(アントラークラフツ)】というジビエ事業をはじめた。現在は、音楽プロデューサーの小林武史さんが実行委員長を務める芸術祭“Reborn-Art Festival”の食プロジェクトの一環として、2017年7月に設立された鹿肉解体処理場“FERMENTO”をその拠点にしている。草木が生い茂った道というほど道らしくない道路を進むと途端に現れるその解体施設は、早朝になると鹿やタヌキなどいろんな動物が顔を出し、夜には満点の星空が見えるほど山と共存した場所にある。

東日本大震災でも被害のあったこの場所に設立されたのは、震災復興の一環でもあり、牡鹿半島を含む石巻全体に繁殖してふえた鹿の命を有効に活用するためでもある。ここ数年、全国的に鹿の生息数が増加しているのはご存知だろうか。それに加えて温暖化や管理されなくなった人工林が増えたりと、さまざまな影響が高じて山は本来の姿を失いかけている。現在の森は、鹿が好む木(エサ)も少なくなり、鹿にとってはかなり生息しづらい。だから人里まで出てきてエサを求めに来るようになってしまった。鹿が繁殖しすぎた原因こそ人間にあるのだが、生態系や森の保善を考えるとこのまま野放しにしてはおけず、駆処する必要がでてきた。しかし元料理人として、その命とそのまま捨ててしまうことに抵抗があったという。だからこそ、こうした食肉処理場の必要を誰よりも感じていたのだ。


狩猟における、良質な鹿の獲り方

早朝、日が昇ると同時に狩猟がはじまる。冬の石巻の朝は氷点下になるほど寒く、いくら着込んでいてもとにかく冷えきった空気が自分にまとわりつく。時間を忘れるほど集中し、神経を研ぎ澄ませ、15:00ころまで全力で山を駆け回るのだが、1頭も獲れないときもあれば一気に5頭まとまって獲れる日もある。小野寺さんの場合、一人で猟をする「単独猟」や、犬と猟師数人が協力して猟をする「巻き狩り」といった銃での猟を行う。鹿を捕まえる手段としては、銃のほかにも「わな猟」があるが、小野寺さんは銃での猟をメインとしているのが特徴だ。

「銃での猟にこだわっているのは、罠と違って捕まえる個体の識別ができますし、必ず仕留められる条件が整ったときにだけ発砲することで、動物にケガを負わせて逃すことなく、ちゃんと一発で仕留められます。そして、人間側もとっても疲れるので猟法の中で一番動物とフェアかなって思っているんです」。この考え方も技も、食猟師としての経験が豊富な小野寺さんだからこそだ。
解体処理施設での丁寧な加工とプロの技


また、小野寺さんは鹿を狩猟したからといってすべてを加工場へ持ち込み、加工し販売するわけではない。弾が身体のどこに命中したのか、食べておいしいと思える個体なのかなど肉質を凝視してレストランに卸せる抜群の質かどうかをしっかりと判断し、そのプロの目の基準をクリアしたもののみを商品にしている。また、猟場が山奥すぎて車まで獲った鹿を運べないけれど良質な鹿が獲れたときは、その場で解体してリュックに入るだけ持って帰ってくる。これは、鹿肉処理解体施設内にあるテストキッチンで料理人が遊びにきたときに試作用の食材として活用している。

彼が鹿肉を捌くときは、包丁や台もしっかりとアルカリ電解水やお湯で消毒しながら作業する。他の猟師がこの作業している現場を何回か見たことがあるが、比較すると明らかにひとつひとつが丁寧だ。皮と肉に分けながらカットしていく作業では、極力肉に傷をつけないよう細やかに、そしてスピーディーに作業する。そうして一通り加工された鹿肉はようやく製品へと形を変えていくのだが、ただパッケージングして終わりではない。その鹿を獲った日付、獲れた場所、鹿の性別、鹿の年齢をすべてメモに残して必ず味見まで行う。「食べてくれる人や調理してくれる人が誰なのかを頭に浮かべ、その人の好きな肉質にするために水分量を調整したり、肉を休ませたり、できるだけクライアントの要望に応えられるようにしています」と小野寺さん。猟だけでもかなりの体力を消耗する中、ここまで手間暇をかけてクライアントに対して徹底した対応ができるのは、料理人との間にしっかりと信頼関係があるからだろう。
写真/沼田 孝彦・小山 ちひろ 文/遠藤麻矢