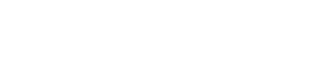親から子へ、家族で守り続ける「食べておいしいいわて牛」の追求

県内のほぼ全域で肉用牛の生産が行われている岩手県。「いわて牛」は東京食肉市場で開催される全国肉用牛枝肉共励会で全国最多の11回も日本一に輝いているトップブランドだ。「いわて牛」とは、岩手県を産地とした黒毛和種で、そのほとんどが岩手生まれ岩手育ちで、生産履歴のはっきりした安心、安全の牛肉として全国に知られている。県内各地では、全国区の知名度を誇る前沢牛をはじめ、江刺牛、きたかみ牛といった地域ブランド牛も充実している。これらも全て、「いわて牛」を支えるブランド牛のひとつである。
岩手県内で黒毛和種の生産が始まったのは昭和初期にさかのぼる。中国地方から優秀な雌牛を導入するところから始まった。肉用肥育が本格的に開始されたのは戦後、1955年頃とされている。その後に前沢牛など、ブランド牛の生産が各地で活発化し、1990年には県内の各地域で生産される銘柄牛の総称として「いわて牛」と呼称することになった。

「いわて牛」が高い評価を受けるに至ったのは、3つの秘訣がある。それは澄んだ空気と美しい水、そして肥沃な大地だ。国土面積の4%を占める、本州最大の広さを誇る岩手県は、県内最高峰の岩手山を中心に広がる山々に囲まれ、東北最大の規模を誇る北上川などの清らかな河川が三陸の海へと注ぐ。
そんな豊かな大自然が多くの恵みをもたらし、米どころ特有の良質なワラなど家畜の粗飼料生産を可能にし、それが牛舎に運ばれて、たい肥や有機肥料づくりの素となる。こうした自然循環型農業の実践と、水田への堆肥施用が全国平均を大幅に上回っていることからも、いかに環境に配慮しているかがよくわかる。

そしてもうひとつ、「いわて牛」の人気を支える大きな要因が一頭一頭を慈しむ、畜産農家のきめ細やかな愛情だ。岩手県の畜産農家たちは我が子のように牛を可愛がり、心血を注いで最高の肉質をもたらす。優れた肉質、豊かな風味。一度味わうとそのとろける味わいにやみつきになる。

黒毛和牛の飼育が盛んなのが県南地方で、奥州市では前沢牛、奥州牛、江刺牛といったブランド牛が飼育されている。
奥州市江刺に牛舎をかまえる菊地畜産も、「いわて牛」のトップブランドとしての信頼・信用を支える畜産農家のひとつ。同市を代表する「江刺牛」の生産農家として、7つの牛舎で300~320頭の牛を飼育。このほか約30頭の自家繁殖も行っている。
「良い牛を育てるには目利きも必要です」と語ってくれたのは菊地畜産の菊地毅さん。
牛の飼育は、まず子牛市場での買い付けから始まる。10カ月程度の子牛を購入し、牛舎で育て、約20カ月、長くても23カ月かけて出荷する。この最初の段階で、牛の見極めが求められるという。

「大人になってがらりと変貌する牛はそういません。上質の肉を求めるには、どんな子牛を仕入れるかも大切な仕事です。子牛の段階で、この子はこういう牛に育つかなと、ある程度想像して仕入れています。牛のどこに注目するか、見方は各農家それぞれ異なります。環境や育て方、仕上がりに対する方針など違いますから。私の場合は、父から教えられたものなので、それを実践しているだけですよ(笑)」。

菊地さんの父・達さんは菊地畜産の社長。1970年代に創業し、江刺牛の創成期を支えた草分け的存在。熱心に自分の舌で確かめながら、脂質の良さを追求し続け、全国枝肉共励会(雄の部)で2回最優秀賞を受賞し、江刺牛、ひいては「いわて牛」を今日の地位に引き揚げた立役者といえるレジェンド。現在、菊地さんは、父の熱意を受け継けつぎ、指導を仰ぎながら、兄達とともに家族で、時代の求めるものに対応しながら研究を続け、さらなる「食べておいしい江刺牛」を追い求めている。
そんな菊地さんも2015年、第15回いわて牛後継者枝肉研究会で出品した枝肉が最優秀賞を受賞。「牛本来の能力を十分に引き出し、近年稀に見る肉質、脂質であり、食べたいと感じさせる枝肉」と大絶賛の評価を得たプロフェッショナル。父の熱意は確実に次世代に伝わっている。
牛一頭一頭の体調管理に気を配り、欠かせないのは朝と晩の“往診”

子牛を仕入れ、牛舎にやってくると、飼育で一番大事な作業である「腹づくり」が始まる。
「生後10カ月ぐらいで来ますから、まだ体ができていないんです。その後、ウチの場合、(出荷まで)約20カ月間はここ(牛舎)にいるものですから、最初の段階でのちのちしっかりエサを食べられるようなお腹を作らなきゃいけないんです」
最初の3か月間くらいはワラや乾草などの粗飼料をしっかり食べさせる。するとお腹が張ってきて、体内の微生物が増えてくる。
「牛の胃袋にはもともと微生物がいて、その微生物がエサを消化します。その微生物の力を最大限に生かすことが狙いで、微生物がいないとエサを食べてもらえません。エサの食いつきがよければ、サシ(脂)の入りもよくなりますので、腹づくりはとても重要な作業ですね」

江刺牛は、さらっと口どけの良い脂質が特徴。最高の脂質を追求するために、飼育で一番気をつけているのは、牛一頭一頭の個体管理だという。それには365日、7つの牛舎をまわる朝晩の“往診”は欠かせない。牛たちの顔色、表情、動作などに異常はないか細かく確認する。
「エサを食べなくなったら、何が原因なのか考えます。ちょっとお腹が荒れているのかな、あるいは肝臓が弱っているのかな、と。ビタミンが低下しているとなれば、ビタミンが入っているエサで調整してみようとか、症状に応じて対処しています。そうなる(症状が出る)前に健康でいられるよう管理することを心がけていますけどね。そのためには、わずかな変化に気づくことが大切。牛と向き合うというか、コミュニケーションは必要です」
管理のために飼料にも気を使う。ワラは地元・米どころ岩手の良質なものを使用し、乾草はわざわざアメリカから輸入している。いろいろ試した結果、「硬い草で栄養がある」との理由で採用することになった。

一年を通じて飼育に緊張感が走る季節は夏。畜産にとって大敵は牛にかかるストレス。牛がイライラしてくると、周囲の牛に角をぶつけてしまうなど、闘争的な行動をとることがある。ぶつかり方次第では、牛が傷ついてしまって商品価値が下がることに繋がる。全国的に一般的な肉牛は大きくて1トン前後だが、菊地畜産では600~850キロと小ぶりが特徴。牛のケガは希少な肉牛を損失する一大事だ。暑い夏は、そうしたトラブルの種が生まれやすくなる。

「夏の間は大変ですね、東北の岩手県もかつてより暑くなってきましたし。もちろん、牛舎の窓や扉を全開にして、扇風機をかけて換気は欠かしません。温度調整には気を使いますが、完璧ではありません。温暖化も進んでいるし、暑さ対策はまだまだ課題が残っていて、研究や対策改善の必要はありますね」
このほかにもストレスを抱えるとうまくエサが食べられなくなるケースもあるという。当然発育が悪くなり、上質の肉はできなくなる。
「単純ですけど、しっかり食べた後、寝て、起きて食べて、また寝て。その繰り返しがいいリズムですね。例えば、寝てなくて立ってウロウロするのは体調が良くない証拠なんです」

菊地さんが飼育していて理想とするのは、牛の体型を俵型に仕上げること。
「俵型になると、枝肉(牛から皮や内臓などを取り除いた状態。形が木の枝に似ていることから)のつくりもいいですし、背中からお尻にかけて、くの字になるような感じになると、サシが抜けていて、いいなって思いますね。しっかりとお肉がついているし、ほどよくサシが入っているのでやわらかいんです」

仕上がりを気に掛ける菊地さんは、定期的に出荷した自分の牛を扱う飲食店で注文したり、スーパーで購入したりと、自分の舌で品質チェックを行っている。
「脂がしつこくないので食べても飽きないお肉。きめが細かいのもあるけど、肉のうま味がしっかりと味わえます。子供達に食べさせると一番正直ですね。小さい子でもステーキ一枚ぺろりと食べちゃう。理屈抜きに食べられるのがバロメーターになっています。全国の皆さんにもぜひ、おいしい「いわて牛」をたくさん召し上がってもらいたいですね」
古より伝わる文化と雄大な大自然の恵みを感じられるみちのくの街

平成18年に合併して誕生した奥州市。周辺の平泉町、一関市と同様にかつて約100年にわたって栄華を極めた奥州藤原氏の足跡が残る。平泉に残る中尊寺を中心とした多様な寺院・庭園などの遺跡は世界遺産に登録されているなど、有形・無形の文化・史跡が残る地域である。
一関市の厳美渓は、神秘的な観光地・景勝地のひとつに数えられる。一関市内へと流れる磐井川が長い時間をかけて浸食して形成された渓谷。エメラルドグリーンの水が流れ、それを奇岩、巨岩、甌穴、深淵、滝などが囲み、約2kmにわたる渓谷美を描いている。かつては伊達政宗が景勝地として認め、年間100万人以上が足を運ぶほどの人気スポットだ。


平泉町に残る別當達谷西光寺の達谷窟毘沙門堂。801年、征夷大将軍・坂上田村麻呂が蝦夷平定を記念して、毘沙門天の加護と京の清水寺をまねて108体の毘沙門天を祀り、国を鎮める祈願所として毘沙門堂と名づけた。東西の長さ約150メートル、最大標高差およそ35メートルの毘沙門堂は2回にわたって焼失し、現在のものは1961年に再建されている。毘沙門堂西方の壁面に顔の長さ3.6メートル、肩幅9.9メートルで刻まれた「岩面大佛」(磨崖仏)も必見。全国で5本の指に入るほどの大きな像で「北限の磨崖仏」として知られている。


奥州市の中央には北上川が流れ、北上川東側には田園地帯が広がり、緑と水が豊かな自然が広がる。この大自然が生み出す作物が良質な飼料を生み、飼料が上質な堆肥へと変わる。そんな自然の恵みをたっぷりといただくことで豊かな農作物が育ち、多くの文化が発展した。農畜産物で例を挙げるなら、江刺牛や前沢牛、奥州牛などの「いわて牛」をはじめ、米、りんごも名産。あんかけうどんや奥州はっと(すいとん)、岩谷堂羊羹、はとむぎ茶は名物・お土産として知られる。工芸品も充実している。奥州藤原氏の全盛期に始まった鋳物づくりの伝統を守る南部鉄器や、初代藤原清衡公が産業奨励した時代が起源とされる岩谷堂箪笥も要注目。奥州市には歴史、文化、グルメ…と旅の魅力のすべてがつまっている。
【有限会社菊地畜産】
電話番号:0197-35-1779
住所:岩手県奥州市江刺愛宕字新川58
写真/海保竜平 取材・文/内山賢一