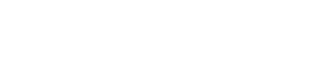【クルックフィールズ】の根底にあるパーマカルチャー
東京都心からクルマで約1時間。千葉県木更津市の小高い丘に囲まれた場所に、2019年11月2日、サスティナブル・ファーム&パーク【クルックフィールズ】がオープンした。東京ドーム6個分という広大な敷地にはオーガニックファームのほか、酪農場、養鶏場、チーズ工場、ダイニング、ベーカリー、シャルキュトリー販売所、さらには宿泊施設やアートが揃い、訪れる誰もがサスティナブルの心地よさや“いのちのてざわり”を体感できる。取材当日はあいにくの空模様であったが、場内の草木や作物は雨粒を受けてきらきらと輝き、生命力に満ち溢れているように見えた。
今回、この【クルックフィールズ】を訪ねた目的は、ここで“何ができるか”はもちろん、ここが“どのようにしてつくられたのか”を掘り下げること。そのキーワードのひとつが「パーマカルチャー」だ。

パーマカルチャーとは「パーマネント(永続性)」と「アグリカルチャー(農業)」、そして「カルチャー(文化)」を組み合わせた造語。持続可能な農業をもとに持続可能な文化、つまり人と自然が共生する関係を築いていくためのデザイン体系のことで、その概念はオーストラリアのタスマニア大学で教鞭を執ったビル・モリソンと生徒のディビッド・ホルムグレンによって1979年に確立された。サスティナブル・ファーム&パークである【クルックフィールズ】では、それがパーマカルチャーデザイナーである四井真治さんの監修のもとで実践されている。
そもそもの発端は【クルックフィールズ】のプロデューサー・小林武史さんの構想に四井さんが共感したことにある。「ap bank
fes」などを通じて環境問題に取り組んできた小林さんが「サスティナビリティの必要性を主張するだけでなく、自分自身が実践していきたい」との思いで有機農業をはじめ、その木更津の荒野を四井さんが訪ねた際に小林さんと対面。小林さんの「ゆくゆくはこの地にサスティナビリティを体験できるような施設をつくり、少しでも興味を持って足を運んでくれた人がサスティナビリティの大切さを考え、行動することが大事だと思ってもらえたらうれしい」という話に賛同したそうだ。それには理由がある。なぜならば、四井さん自身も日本のパーマカルチャーを実現すべく、それを実践して暮らす人であったからだ。

人と自然が共生して循環することで、環境はどんどん良くなる
四井さんは山梨県北杜市で築30年ほどの古民家に家族4人で暮らし、パーマカルチャーを実践している。たとえば増えすぎた竹林の竹をヤギの餌や燃料などに利用し、きれいになったところに畑をつくる。そして、作物を食べて、排泄して、落ち葉や雑草などと共に堆肥にすることで畑に還し、その土で育てたものがまた体の中を通り循環するいう具合だ。「堆肥は循環の基本」と四井さんは言う。台所の排水も微生物と植物の働きで分解吸収させ循環させているそうだ。
そして、こうした循環の仕組みが【クルックフィールズ】の土づくりにも活かされている。
具体的にはこうだ。場内で発生する雑草や収穫できない野菜は飼料にし、動物の排泄物は堆肥舎で発酵させて堆肥にする。刈り取った雑草は、コンポストに集め、虫や微生物によって分解し、また堆肥にする。それらを土に還して畑をつくり、作物を収穫したらたとえば場内のダイニングで料理に。ダイニングの一角には生ゴミを堆肥化する「みみずコンポスト」を設置し、新たに畑の肥料とする。四井さん曰く、「こうした循環を繰り返すことで微生物などの多様性が増え、土壌はどんどん良くなっていく」そうだ。



四井さんの話を聞きながら、あることに驚かされた。それは【クルックフィールズ】に公共の上下水道が引かれていないという事実だ。飲み水は井戸水。各施設の排水は、地下に設けられた浄水槽にて微生物を介し有機物に分解してから、さらに場内に造成した水質浄化システム「バイオジオフィルター」を通し、分解、ろ過。それからマザーポンドと呼ばれる池に注がれる。そして、太陽光発電を利用した電動ポンプでマザーポンドの水を丘の上まで汲み上げ、また場内の小川に流す。ここでも“循環”が行われているのだ。

この「バイオジオフィルター」が素晴らしい。浄化を担うのは微生物と植物。化学薬品は不使用。小川に多孔質の石を敷き、そこに棲む微生物が水の汚れ成分を分解したものを植物が栄養として根から吸収することで浄化する。水がきれいになるだけでなく生物の多様性を生む仕組みでもある。四井さんは言う。
「一般的に生活排水はよくないものとして下水道に流してしまいますが、ここでは人が集い活動することで出る排水は生きものたちが必要な水や養分として活かされる仕組みとなっており、小川や池、畑の土壌、森や草原に棲む多様性のある生きものたちを増やし環境をより豊かにするのです」
なんということだろう。いかにも逆転の発想だ。四井さんはさらに言葉を続ける。
「環境問題においては、人間は環境を破壊する存在と捉えられがちですが、それは人間の存在価値を否定することになります。人間がいることがほかの生物の暮らしを助け、環境をよくすることも可能なんですよ。大切なのは自然の仕組みに沿って社会をデザインすること。そうすれば必ず良くなるはずです」。

「いつかはマザーポンドをきれいにしたい」と四井さんは語る。大元を辿れば、それこそが四井さんが【クルックフィールズ】を小林さんと共に手掛けるようになったきっかけだ。【クルックフィールズ】構想の実現に向けた取り組みがスタートする際、敷地内にあった大きな池の水をきれいにするという話が持ち上がり、機械に頼ってスピーディにやるのではなく、自然界の力を借りて水を循環させながらきれいにするという四井さんの提案が採用されたのだ。時間はかかるかもしれない。だが、場内の小川に流れる澄んだ水や、そこに生息するさまざまな命を身近にしたら、それも不可能な話ではないような気がしてきた。
思えば、人と自然の共生は里山では当たり前のように行われてきた。本来はとてもシンプルなことなのに、特に都市部では物事が入り組みすぎて難しくなっている。
「新しいものや新しい産業にばかり目がいく社会は変化が早く不安定で文化が定着しない」と四井さんは語る。そうかもしれない。人が自然と共生することを意識して暮らせるようになれたら、環境は良くなり、それは無意識に温故知新となり文化が生まれサステナブルな社会となるのだろう。
【クルックフィールズ】の場内には、草間彌生をはじめ、ファブリス・イベールやカミーユ・アンロなどの手による現代アートが多数展示されているが、【クルックフィールズ】のようにサスティナブルで豊かな自然がある場所だからこそ、人の営みであるアートが映える。そう思えてならなかった。

写真/木村文吾 取材・文/甘利 美緒