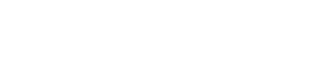在来種に自然農法。世界で通用する日本茶を目指して

日本人の食卓に欠かせない緑茶。世界中にお茶を飲む文化はあれど、蒸して発酵を止めてつくられる抹茶や煎茶、玉露などの緑茶は日本独自の食文化だ。
そもそも、日本の茶の歴史は奈良時代に遡る。諸説あるが、遣唐使が中国から薬として持ち込んだのが始まり。その後一旦茶の文化は廃れたものの、室町時代の勘合貿易で再びお茶や唐物の上質な茶器などが持ちこまれると、一気に嗜好品としての茶の文化が花開く。そして同時期、京都栂尾・高山寺の僧、明恵が栄西から茶の種を譲りうけ栂尾の地に撒き、茶の普及のため宇治の地に茶の木を移植したことが、宇治が茶の産地となるきっかけだった。さらに三代将軍足利義満は、「宇治七茗園」と呼ばれる優れた茶園を宇治に作り、ますます茶の栽培が盛んになっていく。
そのころから、宇治は極上の日本茶の名産地として現在に至るまで長い歴史を刻んでいる。今回取材させていただく、北村 翔さん(32歳)は、そんな宇治・白川地区で江戸時代から300年続く茶農家の十五代目だ。

学生の頃は旅が大好きで、バックパッカーとして世界中を旅行していた北村さん。大学を卒業しても“大変そうだから”と、家業を継ぐことにはまったく興味がなく、国際物流業界の会社に就職した。
家業に気持ちが向いたのは、ベトナムへ一年駐在したことが大きいという。海外に暮らし現地の人たちと話をすることで、自分が当たり前だと思っていた茶畑の風景や、お茶の歴史や文化が価値あるものだと気づいたのだ。
けれど、それを生業にしようとは思うのはもう少し先のこと。ベトナム駐在より帰国後に、ベトナム人・ミャンマー人技能実習生の紹介事業を共同経営という形で運営。事業をしながら、日本のみならず海外の人にも宇治茶の魅力を知って欲しいと茶畑の様子をSNSでアップしたり、海外の友人を実家の畑に案内する活動を少しずつ初めていた。
“自然農法”のきっかけは、茶畑を訪れたイギリス人の一言から

そんなある日、SNSを通じて畑を見学したいというイギリス人の男性から連絡を受けた。快諾して案内をしたところ、「この畑では農薬を使用していますか?」と聞かれ、「はい、農薬を使っています」と答えたときに、北米やヨーロッパでは農薬を使用しないことが購入を左右する大きな指標となることを聞き、驚いたのだという。
「宇治茶の魅力を世界に知ってもらいたいと思っていたところ、世界では、有機栽培であることが大切だという事実に衝撃を受けました。そのとき、日本が誇るお茶の産地で、まだほとんどの農家がやっていない方法で世界に通じるお茶をつくってみたい。そう思ったんです」と北村さんは笑う。

日本茶の生産は、有機肥料を中心に、化成肥料と農薬を使って育てるのが主流だ。そもそも嗜好品ゆえ、その昔から茶葉はさまざまな肥料を使い“味をつくる”ことを工夫しながら育てることが常だった。肥料を上手に使い、味をのせた茶葉がいい茶葉として高値で取引される。けれど肥料を使えば、虫はどうしてもきてしまう。虫との戦いの歴史の中で化成肥料を使い、農薬を使って除去するということは生産性を上げる上で欠かせないこととなっていった。「山庄北村製茶場」も2016年まではすべての茶畑に、有機肥料及び化成肥料と農薬を使ってお茶の生産をしていた。

そうした歴史と伝統の中で、うまみのもとになる化成肥料を使わず農薬を使わない自然農法に切り替えるというのは、日本茶作りの常識を覆す無謀とも言える行為。せっかく作っても、市場で売れないかもしれない。その前に無事に茶の木が育たないかもしれない。そんなリスクがありながらも思い切って自宅の裏の畑をすべて自然農法に切り替えようと思えたのは、「兼業農家」として経営する別事業の収入があったからだという。
父親の北村庄司さんに、「北村家の在来種茶園で自然農法にチャレンジしたい。茶畑からの収入が減っても、僕の会社の収入でまかないます」と思い切って話してみると、すんなりと「やってみたら」と背中を押してくれたのだそうだ。
「育たない」「売れない」無謀とも言える、自然農法の茶栽培
現在「山庄北村製茶場」が生産しているお茶は、自然農法で作った在来種の「三百年煎茶」「三百年玉露」そして、化成肥料・農薬を使用する従来の農法で育てた“ごこう品種”の「ごこう玉露」がある。自然農法の畑は家族で管理し、「ごこう玉露」の畑は知り合いに管理を委託している。自然農法の畑仕事は基本的に翔さん、父親の庄司さん、母親の邦子さんの家族三人で行っている。

一番の苦労は?と聞くと、「自然農法は、日々雑草との戦いです。抜いても抜いてもすぐに生えてくる。特に笹がやっかいですね。雑草は茶摘みのときの障害になるんです。普通に生産していたときには、この畑で1tの収量がありました。化成肥料をやらないとやはり成長も遅いですし、摘める量が減ってしまって今は収量が75kgです。そこから製茶するとおおよそ五分の一になるので、製品になるのは15kg。というわけでお恥ずかしながら、人件費を捻出する余裕がなく茶摘みを現在は機械で行っています」と答えてくれた。

さらに、こうして苦労した茶葉を売るにも壁があるのだという。「宇治在来種が消えた理由は、安定した品質でないと市場で適正価格で販売されないという現状があります。種から生まれる在来種は木によって個性が違う。 でも、接木で品種改良したお茶なら均一な味わいのお茶が収穫できます。だから皆、接木のものを栽培する。自然農法が難しいというのも、その年の気候や環境によって味が変わってしまうことが挙げられます。ですから、木の個性が出る在来種かつ環境に左右される自然農法でつくるうちのお茶は、通常の流通経路で販売するのではなく、ホームページや、SNSを通じて興味を持ってくださった方に直販という形で細々と販売しています」。
農園の宝、宇治在来種・推定樹齢300年の茶の木とともに

家族で管理している自然農法の茶畑にある茶の木は、「山庄北村製茶場」が始まった時に植えられた推定300年の古木がほとんど。しかし、訪ねてみると驚くほどになにげない佇まいだ。機械詰みのため樹高は低く剪定されているが、根っこはかなり深いところまで伸びているのだという。
「ここの畑は初代から続く畑です。この柿の木ですが、「庄治郎柿」と呼ばれ、初代庄治郎が茶畑を作ったときに植えたと聞いています。柿が実る秋には、熟して実を落す。それが肥料となって茶の木を育てる。ご先祖さん、よく考えているなあって感心してしまうんですよね。ですから、化成肥料は与えませんが、秋にススキを刈って茶畑に敷いて肥料にするなど化学品がない時代はどうしていたかなって思いを馳せて工夫して育てています」。
そこが茶畑であることを忘れてしまうような、茶の木と野花や野草が共存する畑。その真ん中に大きな枝を広げる柿の木を愛おしそうに眺めながら、北村さんはそう話す。
「種から生まれた在来種の古木で自然農法をしていると、その土地ごと、種ごとにお茶も全然味が違うということがとても面白く感じます。それは茶の木それぞれの個性なんですよね。ワインのテロワールと同じようにその土地を味に反映する。もちろん気候によっても味は変化します。それは味に“ばらつきがある”というマイナス評価ではなく、個性としてプラスの価値になると確信しています。だから、うちではご先祖さまから受け継いできた古木のお茶を製茶した後、畑ごとの“シングルオリジン”で販売しているんですよ」。

振る舞ってくれた水出しの「三百年玉露」をいただくと、口の中に5月の風が吹き抜けるような青々とした爽やかな香りが広がる。光合成を抑制してつくった玉露ならではの甘みも、ほどよい苦味も感じる。けれど、通常の玉露のような“出汁っぽい”うまみはいい意味で主張していない。そこには300年生き抜いてきた、茶の木の包容力ある優しい味わいが満ちていた。
“おいしい!”と思わず声をあげると、「おいしいでしょう。さっぱりとした味、そして香りがいいね」と北村さんの父・庄司さんが目を細める。

「実はもともと少ない在来種の畑が、生産者の高齢化にともないますます減っているのです。そうした先人たちから伝わる貴重な畑が耕作放棄地になったところもある。こうしたお茶の素晴らしさを一人でも多くの人に伝えて、茶の価値を上げて農家の利益に繋げたいです」と北村さん。
しかし、個人でやっている専業農家の方々は日々の作業に追われて、新しい試みを行う余裕はとてもじゃないけれどない。だから兼業農家である自分が宇治茶の多様性を発信し、未来につなげていく役割があるのだと語ってくれた。
「僕は決して農薬や化成肥料を使う従来のあり方を否定しているわけではないです。家族単位で経営している茶農家が生き残っていくためには、生産性をあげて良質なものをつくるのは当然のこと。けれど、そこに多様性をつくり、商材産地を超えた農家同士の横の繋がりをつくり、もっといえば異業種の人を巻き込んで人材不足や利益確保の新しい形をつくれたらいいなと思っています」。
撮影/大道雪代 取材・文/山路美佐