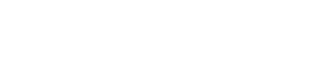虎ノ門ヒルズステーションタワー最上階、“記憶に残る”料理のためのセッティング 北村シェフが大好きな「ガウディの曲線美を北欧の解釈で」とオーダーしたドア。自動で開くことで期待感を高める
――まだ出来立ての香りのする新しいビルの最上階。エレベーターも、この階は【アポテオーズ】だけにつながるプライベートエレベーターになっていて、特別感がありますね。どんなコンセプトのお店なのでしょう?
フランスで15年間働いてきたので、日本の食材をメインに使い、フランスでやってきた料理人だからこそ出せる、パリで提供されているような“時差のない”フランス料理を出していきたいです。それに加えて、五感での体感をすごく大事にしています。「記憶に残るレストラン体験」を提供できたらすごく嬉しいなと思っています。
――お店に入ると、ふわっとヒノキの香りがしますね。アロマで迎える、五感を刺激する空間も意識されているのでしょうか。
香りはレストランに入ってきたときの最初の印象で、記憶にも残るものなので大切にしています。僕自身、ヒノキの香りがすごく好きで、今回、アロマセラピストの「アロナチュラ」山内みよさんとお話しをし、“北村啓太”という香りがどうなるのかを3種類ほど提案してもらいました。その中からお店に合う香りはどれかなのかをみんなで議論して決めました。
寺にある苔むした庭園のような、落ち着いた緑色の椅子に腰掛け、丁寧に淹れられた「さえみどり」のお茶を一服
――レストランに入ると、テーマフレグランスの香りがするというふうになっているわけですね。
そうですね。
香りの後は、今度は音を聞いていただきます。ウエーティングルームで最初に、本当に少量なんですがお茶をお出しします。食事をする前にいったん都会の喧騒からレストランに来た感覚に、リセットして欲しいと思って。日本にはお客様をお迎えするときにお茶をお出しする文化がありますし、自分にとってお茶はお寺のイメージが湧いてくるので、個人的に好きなお寺である、京都の仁和寺に、サウンドクリエイターの方々が音を拾いに行ってくれて、そこで拾ってきた音とピアノでオリジナルの曲をつくっていただき、それを流しています。その音を聞きながらお茶を飲んでもらう。自分の好きな景色と香り、音、すべてこの場に凝縮して、北村啓太の世界観に入り込んでもらおうという意図があります。
――ウエーティングルームからの流れもおもしろいですね。
いろいろ仕掛けをしたい、レストランを体験として楽しんでもらいたいという思いがあったので、レストランの扉を開けてまずは厨房の間を通っていただきます。通路を挟んで片方が温菜、もう片方が冷菜を出すスペースなのですが、そのちょうど真ん中を通ってもらうことで、「わ、
厨房の真ん中だ!」という驚きや楽しさを体験してもらいます。
キッチンは一口だけガスがある以外はオール電化。こだわりの詰まった厨房は、真っ先にデザインした
――キッチンで一番気に入っているのはどの辺りですか?
全部ですが、一番こだわったのは、スタッフ間のコミュニケーションが取りやすいこと。料理人って生涯の中で厨房に一番長くいるので、その空間が心地よく、働くスタッフが誇りを持てるものではないと駄目という考えがあるので、キッチンを重要視したデザインにしてもらっています。
「新しくて、おいしい」が好きで目指した料理の世界 「新しくておいしいものに出会えるのが嬉しくて」目指した料理人の道。「料理で一番になる」と心に決めた
――さて、ご自身のことについても教えてください。料理人の道を選ばれたきっかけは?
食べることが好きで、3歳ぐらいの頃には「コックさん」になりたいと言っていました。新しくておいしいものに出会うのがすごく嬉しくて。つくることが好きだったというよりは、お客側だったので、料理人になればその世界がもっと広がっていくだろうと思って料理の道に入りました。
――実際に働いてみていかがでしたか?
めちゃくちゃ厳しかったです(笑)。恐らく成澤シェフ史上一番厳しい時期だったのではないかと思うので、とにかく怖かったですね。掃除から全部教えてもらったんですよ。成澤シェフが自ら床に膝をついて掃除してるのを見て育ってきたので。初期の頃だったのでスタッフも少なくて、僕は1対1で教えてもらえた。すごくラッキーだったと思います。
フランスで15年「シーズンの捉え方も気候も違う日本を学ばなければ」と帰国後は毎日生産者に会いに行った
――成澤シェフはすごく生産者さんを大切にされていて、先日行われた20周年のパーティでも、20年以上取引のある方など、大勢生産者の方がいらしてましたね。
生産者の方との接し方は、成澤シェフがお手本です。今回フランスから帰ってきて、最初にしたことは、全国の生産者の方に会いに行くことでした。その“おいしいもの”と、その“生産者の方たち”は、どんなことを表現したくて、そのような育て方をしてるのか。それを知っておかないと、料理をするときに気持ちを込められない。結局は人と人。単純にいいものをつくっているかでなく、人として信頼できる人たちのものを使っていきたいと思っています。
――非常に大きな影響を受けた成澤シェフの下からフランスへ。そのきっかけとなったのはなんだったのでしょうか?
当時、成澤シェフの厨房は、フランス経験者ばかりだったんです。僕は19歳の新卒で入ったので、厨房でのフランスの話題に全くついていけなくて。フレンチをやっていて本場のフランスを知らずにやっていくのはやっぱりよくないなという思いと、【レ・クレアシヨン・ド・ナリサワ】を卒業して、国内で成澤シェフ以上に教えを請いたい人が正直いなかった。そうなるともう海外に出るしかないな、とフランス行きを決めました。
ビザなしで飛び込んだフランス、ミシュラン一つ星を手にするまで 初めてシェフを務めた、パリのビストロ【オウ・ボン・アクーユ】時代、師である成澤シェフ訪問時の記念写真
――海外渡航の際に一番大変なのはビザだと聞きます。
その当時、フランスは大人気で。ワーキングホリデーのビザに落ちたので、学生ビザに切り替えて準備をしていたのですが、書類の関係上、時間がかかってしまい、待ちきれずに観光ビザで行ったんです。フランス語は分からないので調べて、パリのレストランに直談判したものの、ビザなしなので全部断られて。学生ビザを取るときに語学学校とやり取りをしていたので、その語学学校に連絡をしたら一ヶ月だけ研修できるようにしてくれて。語学学校に通いながら、最初は【ジスレーヌ・アラビアン】という元【ルドワイヤン】の女性シェフがやっているビストロのお店で研修させてもらったんです。
――素晴らしい巡り合わせですね! パリでは三つ星の【ピエール・ガニェール】でも修業されたのですよね。
はい。【レ・クレアシヨン・ド・ナリサワ】の当時は、決まった料理に対して完璧を追求してやっていましたが、ガニェールシェフは料理の仕方があまりにも自由すぎて、決まっている料理を全部壊してしまう。十何種類もあるアミューズブーシュの担当だったんですが、それを「これ違うだろう」って他の料理で使うパーツを使って変えちゃうんですよ。そうなると今度はこっちの料理どうするんですか?と、キッチンがぐちゃぐちゃになるんですけど。で、次の日にまた来て、ひっくり返すんです。
――その後、【エール】で働かれたきっかけは?
もともと【エール】のオーナーと知り合いで、彼はそれまで【メゾンドサケ】という居酒屋をやっていたんですけど、あまりうまくいかないから、ガストロノミーレストランに変えたい、と僕を選んでくれて。当時ビストロノミーがすごく流行っていた時代で、ビストロはワインもバンバン売れますし、どちらかというとガストロノミーでリスクを負うよりかはビストロを選択するオーナーが多かったんです。そんな中、彼は逆にガストロノミーをやりたいという珍しいタイプで。僕も佐々木シェフがいたお店にシェフとして入って5年間が経っていて、楽しいし学びもあったのですが、
ビストロだった。僕はガストロノミーがやりたかったので、ぜひやらせてください、と。
厨房をオール電化にしたため、直火調理には、パリの店でも使用していた「KAMADO Q」を活用
――フランスのガストロノミーの世界はどうでしたか?
楽しかったですが、ビストロでの経験があってよかったと思うこともすごく多くて。ガストロノミーは高級食材を使うので、肉でも使う部位が決まっています。でもビストロは、例えば羊にしても一頭丸々で買って、部位ごとに料理を考えて、パズルみたいに組み合わせてアラカルトやメニューで出していく。そういう経験をしたから、どんな状況でもフレキシブルに対応できる能力がつくというか。それに一日24匹くらい鳥をおろしたり、扱っている食材の量が全く違うので、フレキシブルに対応できる能力やスピード感はビストロで鍛えられて、より高度なことをやる時に困らない技術が持てました。
――【エール】では5年間星をとり続けました。ご自身ではどんなところが評価されたと分析されますか?
自分の勝手な予想ですが、一つ星をとるためには、一定のレベルをずっと保てているかという安定感がまず見られると思っていて。そこにオリジナリティが入って、二つ三つ、ってついていくんじゃないかなと。毎日真面目に当たり前にいいものを出す、ということは徹底してやっていて、そういうところが評価されたんじゃないかと思っています。
未来を見据えて、さらなる高みを目指す 三元豚をフライパンと炭で焼き上げ、季節の根菜のソテーとピュレ、黒オリーブのソースを添えて
――そして、成果を上げ続ける中、日本に拠点を移そうと思われたのは?
まず、僕はオーナーシェフとしてやりたいというよりは、料理人として、ある程度自由に料理に集中したいという思いがあったので、企業と組んでやるのが向いていると思っていたんです。それに、フランスでやるにしてもビジネスパートナーはできるだけ日本人の方がいいっていうのを先輩シェフたちに言われていて、そういう人と巡り合えたらっていいな、とは常々考えていました。
原点である小田原の「八木下農園」の柑橘づくしのデザートは、送られてくる旬の柑橘で少しずつ変化
――ここから頂点を目指していく、ということですね。
僕は料理人のキャリアをスタートしたときから、三つ星シェフは一番という考えがあり、さらに師匠の成澤シェフも「世界のベストレストラン
50」でレジェンドのような存在になっている。僕もそういったところを目指していきたいですね。
撮影 / 今井 裕治 取材・文 / 仲山 今日子 2023.11.27