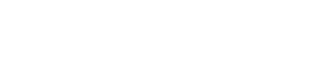経験の集大成。最新店は未来へ繋がる『ファミレス2.0』 2021年7月にオープンした、【BRIANZA TOKYO】店内
――今年7月に大手町駅直結のビルに5軒目となる【BRIANZA TOKYO】をオープンされましたね。今回の店舗は130席。こちらはどんなレストランですか?
一言で言えば「誰もが気軽に来られて、自由にカジュアルに楽しめるレストラン」です。老若男女それぞれの好みがあるのはもちろん、食事制限をしている人、ヴィーガンの人、誰が来ても、食べたいものがある。そして、それは安心できて、体に良いものであることが大前提。そんなレストランのあり方に志を同じくする料理人やクリエイターともコラボレーションしているのも特徴かもしれません。例えば【The
Burn】の米澤文雄シェフや、【The SG Club】のバーテンダー・後閑信吾さんのメニューが並び、BGMはDJ
TAROさんが監修しています。
――コロナ禍での大型店のオープン。思い切られたのではという印象です。この時期の新店オープンになにか考えることはありましたか?
大型店であるということは、新型コロナウイルスによるこの状況を経たからこそ“あり”だと思いました。まず、大型店だと一つの食材をさまざまな料理に使えますので、食材の廃棄率を減らせます。また、誰もが気兼ねなくカジュアルな値段で楽しんでいただくには、たくさんのお客様が来店することが前提でないとできません。サービスの効率化も考え、タッチパネル式の注文システムなども導入しています。
ジョスパーオーブンで焼き上げ、ヨーグルトをたっぷりと使った『ひよこ豆のグルテンフリーパンケーキ〜ファリナータ〜』
――老若男女だけでなく、食事制限をしている人も、ベジタリアンもヴィーガンもみんなが楽しめて、自然に体も健康になり、地球にも優しい。「ファミレス2.0」どころか、「ファミレス3.0」まで行く、時代が求めているレストランですね。
今の時代、ファミレスって、あまりいい印象を持っている人はいないかもしれません。でも1970年代の後半、ファミレスが出来た頃って家族総出で行くことがオシャレだったんですよ。車で行列してまで行く目的は、ただ食事をするだけでなく、その場を楽しむために行く所だったんです。僕の言う“ファミレス”というのは、そうした誰もが楽しくなって、集まりたくなる場所ということ。人が集まるところには、何かが生まれる。そういう場所になればいいなという思いも込めています。
アメリカの大学で経営を学び、企業に勤めた後、料理人の道へ 奥野義幸シェフ。1972年生まれ、和歌山県出身
――奥野さんには、考え方が従来の“料理人”とは違う、ビジネスセンスや視野の広さ、伝えたいことを料理を通じて編集できる力を感じます。なぜそういうことができるのでしょう?
うーん、どうしてか、と言われると、自分ではわからないのです。アメリカの大学で経営学を学び、企業で2年間働いた経験が大きいのかもしれません。もともと僕は、和歌山県の料亭の家に生まれました。けれど、学生の頃は料理人になるとは思っていませんでした。高校の先生に“君は英語ができるから、海外の大学に行くのもいいのでは?”と言われて。アメリカでも、日本人が絶対にいなさそうなサウスダコタ州の大学に入学したんです。そこで経営学を学びました。帰国して、普通に企業に就職したけれど、2年ほど経って、24歳のときに料理の世界へ入りました。
――一旦会社員になって、なぜ料理人になろうと思ったのでしょうか?
単純に
“かっこいい”と思ったからです。実家が料亭だったので飲食業が身近だったこともありました。だから、一旦会社員になったけれど、やっぱり飲食の世界に進みたいなぁと思ったんです。イタリア料理を選んだのも、やっぱりかっこよかったから。当時の1990年代初頭はイタリア料理ブームで、「デートに行くなら“イタメシ”でしょ」って時代でした。
――東京で働いて、イタリアに行きますよね。イタリアへ行くきっかけは?
【ピノッキオ】の後、数店で働いたのですが、その頃から、なるべく早くイタリアに行くと決めていました。今思えば頭でっかちだったと思いますが、やるなら本場で学ばなくちゃと思っていて。イタリア語や文化についてイタリア文化会館で学んでいたときに、イタリアの語学学校を紹介してもらってイタリアに飛びました。
【la Brianza】の店内。地中海を航行する船をイメージした明るいインテリア。ちなみに店名は修業したブリアンツァ地方から命名
――本場イタリアはどうでしたか?
純粋に楽しかったです。言葉が喋れないと赤ちゃん扱いだし、なめられることはあったけれど、日本のような厳しさはなかったです。あと、料理や環境については、日本との共通点を多く感じました。リグーリア州って海も近いし、ハーブや魚介をたくさん使います。僕の実家の和歌山も海が近くて魚もよく食べていましたから。リグーリア州では、タコや魚をシンプルに茹でてオリーブオイルやハーブと食べたりするんですれど、意外とデリケートな味で、それが和食に近いなと感じたりしました。
――帰国してすぐに【la Brianza】をオープンしたのですか?
はい。2000年に【リストランテ la
Brianza】としてオープンしました。最初の2年間はオーナーのもとで代官山に店を出していました。けれど、オーナー夫妻が健康上の理由で店を続けられなくなってしまった。どうしようか、と悩んでいたときに、お店の常連さんで麻布十番にビルを持っていた人が、入居できる店を探していると聞いて、僕が店を買い取る形でオーナーシェフとなり、麻布十番に移ったのです。まさに渡りに船。そして、また縁があって麻布十番の店は別の形態にし、六本木ヒルズの今の場所に、2016年に本店として【la
Brianza】をオープンしました。
経験と出会いで見つけた、本当に求められるレストランのあり方 奥野シェフは【la Brianza】の厨房で腕をふるう
――【la
Brianza】は、イタリアの伝統的な料理のエッセンスを感じる、日本各地の食材を使った、オリジナリティ溢れる料理が登場しますね。お店オープン時からそうした方向性ははっきりしていたのでしょうか。
いや、これが最初の思いから、かなりブレていくんですよ。人間やっぱり成長するじゃないですか。変わるのは自然ですよね。なにが大きく変わったかと言うと、料理に対する考え方。20年前に店を出した当初はイタリア原理主義的な料理にこだわっていました。つまり、「イタリア本場の味をそのまま提供したい」ということです。そこにこだわり、壁にぶち当たってました。
【la Brianza】のスペシャリテ『トリュフのグラタン ピエモンテ風』。卵とパルミジャーノレッジャーノ、ベシャメルを層にして焼き上げ、トリュフをたっぷりと。
――どんな風に変わっていったのでしょう?
店をやって10年くらい経った頃でしょうか。イタリア原理主義的な味をやっていこうとするなかで、ふと「おいしいってなんだろう」と考えるようになってきて。実家は日本料理屋だし、アメリカに住んだこともあって、自分の経験上、“こうでなければならない”とこだわるのは違うのかもしれないと感じたんです。もっと自由な“おいしいもの”って星の数ほどあるよねって。もちろん軸足はイタリア料理です。イタリア料理も愛しているけれど、それ以外のおいしいものも食べたい。経験したい。そんな思いが自分の料理の変化変遷につながっていると思います。
――10年前からだんだん考えが変わったと。
その頃に出会った、随筆家の伊藤章良さんや、タベアルキストのマッキー牧元さんとの出会いも大きかったです。“おいしい”っていろんな形があるんだ、料理だけじゃなくて、いろんな大切なことがあるんだ、と教えてくれました。他にもたくさんの人との出会いが、自分を変えました。その頃から、イタリア本場そのものの味を出すというよりも、みんなが“おいしい”“楽しい”を一番に考えるようになりましたね。レストランに来る人は、料理人や知識人ばかりではないですから。そこから、料理人として何を出したいか、よりも、お客様はなにを“おいしい”と感じるか、なにを‟楽しい”と感じてくれるか、を考えるようになりました。
『夏鹿のラグーナポレターナ パッパルデッレ』。ナポリの郷土料理「ラグー」を壱岐の夏鹿でつくり、たっぷりのハーブと。パスタは手打ちのパッパルデッレ
――日本の生のトウモロコシの甘さを生かしたポレンタや、鹿のハツを思い起こさせるくじらの肉が出てきたりと、イタリア料理だけれど、イタリアにはない料理も多く登場しますね。
お店にいらしてくださる方は日本人が多いので、やはり日本人だったらこうしたらもっとおいしく感じてくれるだろうな、という工夫はしています。イタリア伝統料理的なものから一歩進んで、独自に考えた料理を今はお出ししていますね。
企業のコンサルから海外進出。これからの料理人のカタチとは 【BRIANZA TOKYO】では、奥野さんが開発にかかわった低糖質高タンパクの「ZENB NOODLE」のパスタが食べられる
――お店での運営だけでなく、モスバーガーやブルガリアヨーグルトのコンサルテーションや、「ZENB
NOODLE」の商品開発など、企業とのお仕事も多く手掛けていらっしゃいますが、もともとそうしたことに興味はあったのでしょうか?
いえ、自分では思いもしなかったのですが、これまた不思議で、企業さんのほうから「こうしたお仕事をお願いできないか」と連絡をいただくことが多いのです。基本的に求められると頑張っちゃうタイプなんで、自分がやりたいと思ったことはやらせていただいています。「なんで僕に?」って思いますが、20年真面目にレストランを経営していると、こうしたお話も来るのかなと思ったりしています。ありがたいですね。
――2021年末にはアメリカの複数の出店が決まっているとか。第一号店はサンタモニカだそうですね。これはどういうきっかけで決まったのでしょうか?
これも、先方が突然訪ねてきたんですよ(笑)。連日、怪しい外国の方のグループがお店に食事に来たから何事かと思い、「どうして、うちで食事をしてくれたんですか?」と聞いたんですね。そしたら、マリオットホテルの幹部の方達で、「アメリカ西海岸で、東京のイタリアンを出したいと思っている。ぜひやって欲しい」と言うんですよ。彼らがなぜ僕に白羽の矢を立てたのかは見当もつかない(笑)。けれど、どういう経緯であれ、英語が話せて、東京のイタリアンという先方が求めている店にフィットしたんだと思います。そこで話がトントン拍子でまとまりました。
――アメリカのお店はどんなお店になりそうですか?
特に決めていませんが、「好きにやってくれ」と言われています。僕が料理をするから、自然と“東京イタリアン”というジャンルにフィットしたものになると思います。年末からはアメリカに飛んで、しばらくは向こうでしっかりと地に足をつけてカタチにするつもりです。
イタリア各地から揃えたワイン。ソアヴェやブルネッロモンタルチーノなどのワインが、ハーフで頼めるのも嬉しい。
――その前に、10月には【The Burn】米澤文雄シェフと共同で運営するWEBメディアがスタートするとか。
そうですね。今TikTokとかYouTubeとか、SNSはたくさんありますが、僕は自分自身がつくるメディアにこだわりたかった。今までの僕の経験を、若手の料理人に伝えられるものをつくりたい、と思ったのです。例えば、海外経験のある僕や米澤シェフが考えた“料理人のための英語講座”を開講予定。料理人が自由に国境を越えて活躍するには英語が不可欠ですからね。そのほかにも、いろいろとコンテンツを用意する予定です。楽しみにして欲しいですね。
――お店で料理もして、新規店舗の企画・設計、企業のコンサルテーション、マーケティングに海外進出、さらにオンラインメディアのスタートまで! それを一人でジャッジして、実行してって、ちゃんと寝てますか?
いや、ほんと、そろそろ限界なんです。なので、やっぱり外部の方を仲間にしたいなって思い始めてます。外部って言葉は僕、嫌いなんですよ。なんか責任感がないように聞こえちゃうじゃないですか。でも外の方でも、ものすごく責任感のある方っていらっしゃる。そうした方に出会えてチームビルディングできたら、もっともっと面白い世界が広がるのかなあって思いますよね。まさに、漫画の『ONE
PIECE』の世界みたいにね。
――奥野さんは、料理人の可能性が、ここまで広がるんだという“料理人3.0”を体現している人かもしれませんね。
いろいろ言ったけれど、僕の軸足はあくまで料理人です。毎日店で料理していますし(笑)。でも、経営的なセンスとのバランスはとても大切だと思っています。自分のこだわりを通すのではなく、理想からはずれても、どこに落とし込めばみんなに喜んでもらえるかを考える感覚というか。経営者としての感覚は実家から学んだことも多いです。両親は料亭を営んでいましたが料理人ではなかった。でも僕は料理人。料理人としての思いも、経営者としての考え方もどちらも痛いほどわかるし、それがわかることが僕の強みかもしれませんね。
撮影/今井 裕治【la Brianza】、玉川 博之【BRIANZA TOKYO】 取材・文/山路 美佐 2021.9.7 取材