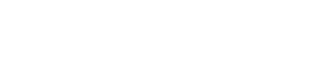料理人としての原点
 「シャトー」の建築には、ロブション氏の故郷に近い、フランス中西部のショヴィニー地方から石材1,000トンが運ばれた
「シャトー」の建築には、ロブション氏の故郷に近い、フランス中西部のショヴィニー地方から石材1,000トンが運ばれた
――料理の道を選ばれたのには、お母様の影響が大きかったとか。
母が料理好きで、りんごがあると生地をこねてアップルパイをつくってくれたりしていました。料理をつくっている様子を見るのも、食べるのも好き、というのが原点ですね。料理人になろうと決めたのは高校生の時です。大学付属の高校に通っていてそのまま大学に進むこともできたのですが、勉強があまり好きではなかったので、好きなことなら勉強できるはずと調理師専門学校に進学。卒業後、ホテルに入りました。朝から夜まで働く大変な仕事という覚悟はできていたので、辛かったですけど、辞めたいと思ったことはありませんでした。
――どんなきっかけでフランスに行こうと思われたのですか?
当時は「ミシュランガイド日本版」が出る前で、三つ星の最高峰のレストランとはどんなところなのだろうと興味があり、20歳のときに1人でフランスへ旅行したのがきっかけです。人生で初めて行った三つ星店がリヨンの【ポール・ボキューズ】で、運よくボキューズさんにもお会いできました。あまりに感動して、もう「フランスに行きたい」としか考えられなくなって。今思うと若気の至りというか、勢いで行ったっていう感じはあります。
 22歳で渡仏、アラン・サンドランス氏率いる【ルカ・カルトン】、【グラン・ヴェフール】など、名店で修業を重ねた
22歳で渡仏、アラン・サンドランス氏率いる【ルカ・カルトン】、【グラン・ヴェフール】など、名店で修業を重ねた
――フランスへの思いは募りつつも、フランス語をしっかりと勉強してから渡られたわけですよね。
仕事をしながらフランス語の勉強はできないと思い、勤めていたホテルを辞めて、日本にあるフランス語の語学学校でみっちり勉強してから行きました。フランスへ渡り、流暢とまではいえないまでも基本的な意思疎通はできたので、かなり助かりました。自分で興味のあるお店に手紙を書いては面接に行き、1カ月ほどで仕事が見つかりました。
――実際に行ってみて、フランスと日本のレストラン、どんなところが違いましたか?
日本では触ったことも食べたこともないような食材が当時は特にたくさんあったので、見るもの触るものすべてにおいて衝撃的でした。
圧倒された「ロブションの料理」
 1ミリ以下の絞り口から、正確なドットを刻んでいく。精緻さとスピード感が当然のごとく求められるのがロブションの仕事だ
1ミリ以下の絞り口から、正確なドットを刻んでいく。精緻さとスピード感が当然のごとく求められるのがロブションの仕事だ
――4年間、フランスのさまざまな有名店で働いたのちに、ジョエル・ロブションさんのところで働くようになるのですよね。働くきっかけは何だったのですか?
実は渡仏してすぐの頃、日本にはすでに【タイユバン・ロブション】があったので、ロブションさんの料理をフランスで無理して学ぶ必要はない、と思っていました。ただ、フランスの多くの有名店で働き、いろいろなお店に何度も食べにいく中で、あまりおいしくない皿がどのお店にもあったのです。でも当時、サンジェルマンにあった【ラトリエ
ドゥ ジョエル・ロブション】では食べた料理すべてがおいしかった。そんなロブションの料理のすごさに惹かれて、働きたいと連絡しました。
――すぐに採用されたのですか?
日本もそうですけれど、ロブションの扉はいつでも開いています。でも、続けていくことが難しい。フランスのお店でも、数日でいなくなってしまうスタッフもいました。当時、朝7時台にお店に行って、夜帰るのが深夜3時近くなることもあったので、労働時間はとても長かったですし。毎日、昼と夜で200名以上のお客様が来店されて、1人当たり平均5、6皿ほど召し上がります。つまり、1日約1,000皿を、10人ほどのスタッフでつくることになります。それはとてつもない仕事量で、10キロ、20キロの舌平目や、1匹が5~6キロもあるチュルボ(ヒラメの仲間)も、1日で3、4匹が消費されてしまうのです。でも、日々続けていくと、それが当たり前になって、いつの間にか仕事が身についていったと思います。
――そういった経験は、今に活きていますか?
さすがに東京でそこまでの食材の量は扱いませんけれど、その時に数をこなしたことはとても大きくて、フランス食材の扱いは慣れていると思います。フランスではどこの店で働いてもキツかったですが、その中でも一番、身に付いたし、自分が成長できたのがロブションです。
――ロブションさんにかけられた言葉で、印象に残っているものはありますか?
料理を試食しているときに、よく「目をつぶって食べなさい」と言われました。「目をつぶって食べて、何を食べているかわからないようだったら、その料理はいい料理ではない」と。あまり手を加えすぎると食材を活かせなくなってしまう。何を食べているかわからない料理は、何よりも食材に対して誠実でないと思うので気をつけています。
 「せっかくなら名前を覚えてもらいたくて、ロブションさんに積極的に話しかけていました」と関谷シェフは当時を振り返る
「せっかくなら名前を覚えてもらいたくて、ロブションさんに積極的に話しかけていました」と関谷シェフは当時を振り返る
――身近なところから見るロブションさんの凄さは、どんなところだと思われますか。
いい意味で、“粗探し”が上手だったと思います。お客様に出せないというレベルではないけれども、いつもよりちょっとよくないな、というところを見つけてしまう。そういう感覚が鋭いと思います。味覚に関しても同じで、常にブレないようにつくってはいますけれども、繊細な違いを感じ取る方だったと思います。それから、その時代にあったものだけではなく、さらに1歩先、2歩先を考えていらした。もしそれが、10歩、20歩先だと奇抜すぎてしまうけれど、時代のちょっと先をしっかりと見据えて、走っている方だと感じていました。
――そんなロブションさんの眼鏡にかない、若くしてフランスの【ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション】のスーシェフに抜擢されたわけですね。
すごく名誉なことではありましたし、日頃の仕事を評価してもらえたのはうれしかったです。パリのロブションで日本人がフランス人の部下を何十人も束ねるなんて、なかなか経験できることではありませんし、すごく恵まれていたと思います。フランス人は、優れたものに対してはきちんと認めてくれるので、実力で示していくしかないと思っていました。振り返ると、評価されたポイントは勤勉さというより、「波のない仕事」だったと思います。特別、できがよい日はなかったかもしれませんが、常に合格点以上の仕事ができていたのかなと。
――そのために心がけていたことはありますか?
仕事とプライベートをはっきり分ける。休みの日は休み、仕事の日は仕事をする、メリハリのある生活を心がけていました。
ほぼすべてのキャリアを積んだフランスを離れ、日本での新たな挑戦
 『牛フィレ肉 フォアグラと抱き合わせローストにし“ロッシーニ”風に仕上げて』。肉は滑らかで上質なシャトーブリアン
『牛フィレ肉 フォアグラと抱き合わせローストにし“ロッシーニ”風に仕上げて』。肉は滑らかで上質なシャトーブリアン
――そして、2009年に東京・六本木の【ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション】の料理長に就任される。フランスに残ろうとは思いませんでしたか?
20代はフランスでずっとやってきたので、30代になったときに、日本で新たなチャレンジをしたいと帰って来ました。でも、もしあのままフランスにいたら今頃どうしていたのだろうと考えることはあります。今考えると、人生の分かれ道でしたね。
――9年弱をフランスで過ごされたということで、日本に戻ってきてのギャップはありませんでしたか?
フランス語でずっと仕事をしていたので、なかなか日本語が出てこず、当初は日本語で仕事をすることが苦痛でした。また、自分の思い通りの味になるのがフランス食材だったので当時はよく使っていましたが、やはり手に入るものが限られる上、届くのに時間がかかるものも多い。そこで、日本の食材を自ら探し、産地を訪問してお話を聞いたり生育環境を調べてみたり、少しずつ勉強をしていきました。日本にしかない食材で料理をつくっていくことに関してはロブションさんもすごく興味を持っていて、見たことのない食材は「これは何?」とよく質問されましたね。フランスに長年いたことで、フランスの食材も日本の食材も両方知っていて違いがわかるというのは、自分の強みだと思います。
 正規代理店からのワインのみ、約2万5,000本が揃う。「高級ワインも安心して開けられる」と、美食家の信頼も厚い
正規代理店からのワインのみ、約2万5,000本が揃う。「高級ワインも安心して開けられる」と、美食家の信頼も厚い
――そしてシェフとして日本でのキャリアを積んでいかれる中、さまざまなコンクールに挑戦されていますね。
部下に対して見本となる仕事をしたいですし、日々の仕事の中だけでは成長しきれない部分が、コンクールという新しい挑戦を通して見えてくると思います。僕1人というよりは、自分たちがチーム全体でやっている日々の仕事がどう評価されるのか、という思いでいつも挑戦しています。ですから、コンクールの成功はチームの仕事が評価されたと感じます。実際、テタンジェで世界一を獲った料理は、六本木の【ラトリエ
ドゥ ジョエル・ロブション】のスタッフはみんなつくれます。こうして技術が共有できるのもうれしいですね。
心の中で生き続ける師の足跡、フランス料理の一流の技術者でありたい
 ロブションさんのシグネチャー『帆立貝のターバン仕立て』。シャトーシャロン(黄ワイン)とコライユの泡のソースを添えて
ロブションさんのシグネチャー『帆立貝のターバン仕立て』。シャトーシャロン(黄ワイン)とコライユの泡のソースを添えて
――中でも「ル・テタンジェ賞 国際シグネチャーキュイジーヌコンクール」での優勝は本当に感動的でした。どんな思いで参加を決めたのですか?
若い頃のロブションさんも優勝した世界的に権威のあるコンクールで、ロブションさんが歩んできた道をたどりたいと思ったからです。ロブションさんが来日した時に、テタンジェにチャレンジしたいと伝えたら、ご自身が獲得したものすごい数の賞の名前を一つずつ挙げて「俺はあれも勝ったし、あれも獲った」と言われて。最後に「勝てないならやるなよ」と(笑)。
――すごいプレッシャーですね(笑)。覚悟を問われるような質問ですが、それを聞いてどう思われました?
実際にロブションさんはそれだけの賞を獲得しているので、もう仕方ないと(笑)。その数に圧倒されつつも、「勝てばいいんでしょ」と心の中では思っていました。
 15年間シェフを務めた「ラトリエ」は黒のコックコート。「視界に入る、白い自分の両袖に、まだ慣れなくて」と笑う
15年間シェフを務めた「ラトリエ」は黒のコックコート。「視界に入る、白い自分の両袖に、まだ慣れなくて」と笑う
――ただ、国内予選を突破し、本選に向けて準備を進めている最中にロブションさんは亡くなってしまうのですよね。
はい。本選の書類を出すために写真撮影をしなければならなかったのですが、その撮影予定日の前日に亡くなられて。そして、その後に発表された課題が、ロブションさんのスペシャリテの一つでもある、「ターバン仕立て」だった。まるで巡り合わせのように感じました。コンクールは“日々の仕事の延長線上”といつも捉えてきましたし、「ターバン仕立て」自体も知っているメニューだけに、どれだけ完成度を上げられるか、また、ロブションさんが完成されたレシピから、自分のオリジナリティあるものに仕上げなくてはならないという意味で、知らない課題よりも難しかったです。
――並み居る強豪のメンバーの中で優勝と言われたときは、どんな気持ちでしたか?
支えてくださった方たちが大勢いらしたので、そういう人たちに良い報告ができて、嬉しいというよりホッとしました。レシピは自分でつくりましたが、ロブションさんに教えていただいた手法ですとか、この料理に限らず、いろいろな料理の中にロブションさんが生きていると思います。もしロブションで働いてなかったら、このコンクールにも出ていなかったでしょうし、あの料理をつくり上げることもできなかったでしょう。心から感謝しています。
――ロブションさんのスタイルは、ご自身の中で生きている。
そうです。ただ僕自身、あまりロブションの料理に寄せようとつくったことがなくて。自分が好きな料理がロブションの料理に近いという感覚です。ただ、ロブションさんもそうですが、世界的に評価されている方の料理は、その料理を見れば誰がつくったかがわかる。いつか、そういうひと皿をつくりあげたい、という思いは強く持っています。
「シャトー」を背負い、師の味を未来につなげていく
 フランスの古城をイメージした、シャンパンゴールドと黒が基調のインテリア。非日常の空間にドレスアップしたゲストが集う
フランスの古城をイメージした、シャンパンゴールドと黒が基調のインテリア。非日常の空間にドレスアップしたゲストが集う
――そして、2021年11月に、日本人として初めて【ガストロノミー
“ジョエル・ロブション”】の総料理長に就任。日本のロブショングループを統括する立場になり、自身のスタイルをより一層打ち出していくことになったわけですね。その根本を流れる「ロブションのアイデンティティ」をどのように捉えていますか?
ロブションさんには「何でこういう風につくったの?」と、よく質問されました。料理の構成食材は基本的に3つで、お皿の上に“必要なものしかのっていない料理”がロブションの料理だと思います。ロブションさんから教えてもらったことをベースに、日本にしかない食材も使った日本人にしかつくれないフランス料理を目指しています。
――ロブションさんも、日本やスペインからインスピレーションを受けながらモダンな料理をつくっていったと思うのですが、関谷シェフの考える現代のフランス料理とはどんな料理ですか?
ロブションさんの料理は見た目の華やかさを評価されがちですけれど、その根底にある「人間が根本的においしいと感じる味」を一番に考えていた方なので、「絶対においしいもの」をつくり続けたいです。今、フランス料理でも軽やかな料理が多くみられますが、おいしくなければ意味がない。軽やかさの中の深い味わいが必要です。時代に合わせた料理も大切ですが、基礎的な技術や知識の部分がないと定まっていかない。ロブションさんはいろいろな所にアンテナを張っていた方でした。職人としての基礎を大事にしながら、時代に合わせた料理をつくっていきたいなと思っています。
 料理の根本にある職人仕事への想い。「ロブションさんが歩んだ道をたどる」決意を胸に、新たな目標に向かって進んでいる
料理の根本にある職人仕事への想い。「ロブションさんが歩んだ道をたどる」決意を胸に、新たな目標に向かって進んでいる
――【ガストロノミー
“ジョエル・ロブション”】はすべてにおいてラグジュアリーなレストランですけれど、ラグジュアリーとサステナブルのバランスの取り方については、どう考えていらっしゃいますか?
もともとフランス料理は、食材をあますことなく使うという意味で、サステナブルな料理だと思います。また、天然の魚が獲れなくなってきている問題に関しては、例えば自分がフランスにいた頃、地中海産マグロの数が少なくなった時期がありました。そんな時に、ロブションさんをはじめ、使うのをやめようと呼び掛けたシェフが大勢いらっしゃいました。やはり、今後そういったことにも敏感に対応していかなくては、と思っています。
――これからのご自身の目標は。
割と飽きっぽい性格なので、いろんなことをやっていきたいのですけれども、やはりロブションさんが歩んできた道をたどりたい。そういった意味で、フランス料理の技術者としての頂点を極めたい。新たな挑戦に向けて、今準備を進めているところです。
撮影/今井 裕治 取材・文/仲山 今日子 2021.12.8 取材