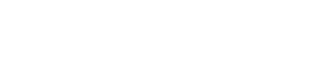新天地「トーキョー」への想い
 香港の建築家アンドレ・フーによる優雅な内装は、“日本の美”をモチーフにしたオーガニックな柔らかな印象。席がゆったりと配されており優雅なひとときを過ごすことができる
香港の建築家アンドレ・フーによる優雅な内装は、“日本の美”をモチーフにしたオーガニックな柔らかな印象。席がゆったりと配されており優雅なひとときを過ごすことができる
――確か2020年の春頃に「東京に拠点を移す」と連絡をもらったと思うのですが、改めて、なぜ東京に来ようと決めたのですか?
じつは、香港に行く前からいつか東京に行きたいと思っていました。これまでもつねに、なぜだかわからないが引き付けられていました。でも、アジアに行ったこともなかったですし、ヨーロッパから東京に行くのは、とても大きなこと。東京の街も大きいですし、さらに日本はとても圧倒的な存在です。深く知るためには、十分な時間を使って事前準備をすることが必要だと思っていたのです。
――香港にいた時も、かなり頻繁に東京にいらしていましたね。
香港で5年の時間を過ごしている間、日本を訪れて準備をしてきました。年に5回は来たと思います。思い切って日本に移住する前の、それは投資のようなものでした。
――去年の11月に来日してからは、国内の多くの場所を訪れましたね。
はい、それを通してたくさんの人のつながりを得ました。とくに、このフォーシーズンズホテル丸の内
東京を監修していた、(モリエールの)中道博シェフには、とてもお世話になりました。中道シェフが多くの生産者を紹介してくれたのです。人というのは、とても大切なものだと思います。
 食事中にサーブされる、こだわりの『サワー・ドゥ・ブレッド』。北海道産のとうもろこしを1週間かけて乾燥させ、香港【ベロン】の開業当初からつくっている天然酵母を使って焼き上げる
食事中にサーブされる、こだわりの『サワー・ドゥ・ブレッド』。北海道産のとうもろこしを1週間かけて乾燥させ、香港【ベロン】の開業当初からつくっている天然酵母を使って焼き上げる
――市場にもかなり足しげく通っているとか。
もちろんです。豊洲には少なくとも週に2〜3回行きます。日本は縦に長い国なので、食材に追いつくためにつねに走り続けているような気持ちになります。日本は間違いなくヨーロッパより季節の移り変わりが早いですし、食材によっては、数日、数週間しかない食材があり、とてもエキサイティングです。つねに、翌年についても考えています。今年使った食材を、来年使うときには、以前よりも20%くらい、使い慣れているかもしれない。その次の年は40%、そして次は60%。そして、いつの日か、95%になればいいと思っています。なぜなら、100%になるということはけっしてないからです。
――日本の食材を理解するのと同時に、いい食材を輸入するための努力もしていますよね。
それが合理的であると思えば、輸入もします。その味に惚れ込み、どうしても日本で使いたかった、ペトロシアンキャビアは、日本で使えるのはうちだけです。それと同じように、日本の名店は、希少で素晴らしい食材を使っていますよね。そんな「ここだけでしか食べられない極上の食体験」も提供したいと思っています。
情熱と勤勉さが道を拓いた
 ロンドン、N.Y.、パリの名だたる名店で腕を磨き、2016年には香港【ベロン】のシェフに。2020年には『アジア ベストレストラン50』で4位に選ばれた
ロンドン、N.Y.、パリの名だたる名店で腕を磨き、2016年には香港【ベロン】のシェフに。2020年には『アジア ベストレストラン50』で4位に選ばれた
――地元のロンドンから、なぜ遠く離れたNYで働こうと思ったのですか?
じつは、もともと行きたかったのは、同じトーマス・ケラー氏が率いる店、【フレンチ・ランドリー】だったのです。彼の料理本を読んで育ったようなものですし、カリフォルニアという見たこともない場所に憧れました。働きたいというメールを毎週送ったのですが、返事が来なかった。やっと返事が来たと思ったら、空いているポジションがないということで、ならばと、NYの【パ・セ】にメールを送ることにしたのです。ついに返事が来るまで、毎週、1年近くメールを送ったと思います。
――まさに、情熱が道を拓いた、ということですね。その後【パ・セ】の最年少スーシェフとなり、若くして高い評価を受けたそうですね。知り合いもいないNYで、どのように実力を示したのですか?
自分は、学校を16歳で卒業してすぐ厨房で働き始めましたから、料理学校に行っていた同年代の若者よりも、キャリアが長かったというのはあると思います。また、勤勉に働く人を認めてくれる環境に恵まれていました。私は家族をイギリスに残していたから、ベストを尽くす責任があると感じて、人生の時間のすべてを仕事に捧げようと思ったのです。私は自分が世界で最も優れたシェフでは絶対にないと思いますが、かわりに、ほとんどの人よりも朝早く起きることができる。それが自分のキャリアを決定づけたし、多くの人と差別化できたのだと思います。なんといっても、時間に正確なイギリス人ですからね。
一切妥協なし。クラッシックな手法、アラミニッツにかける思い
 デセール『宮崎県産マンゴー ショートブレッド クレームシャンティ』。ラム酒でマリネしたマンゴーの中には、メレンゲ、そしてソルベの三層が隠れているサプライズ。たっぷりのバニラビーンズと砕いたショートブレッドの入った生クリームは望むぶんだけサーブしてくれる
デセール『宮崎県産マンゴー ショートブレッド クレームシャンティ』。ラム酒でマリネしたマンゴーの中には、メレンゲ、そしてソルベの三層が隠れているサプライズ。たっぷりのバニラビーンズと砕いたショートブレッドの入った生クリームは望むぶんだけサーブしてくれる
――その後、本場パリで働きたいと、パラスホテル、ル
・ブリストルの【エピキュール】でコミ(通常もっとも経験のない料理人がつくポジション)として再スタートする訳ですね。後悔はありませんでしたか?
正直にいうと、最初の9カ月は、本当にキツかったです。フランス語が話せなかったし、NY時代のバスルームよりも小さなアパートに住んで、お金もなく、友達もいなかった。でも振り返ると、人生でベストの選択をしたと思います。
なぜなら、どう料理をするかを本当の意味で学んだからです。それまでも約10年の料理をしてきて、また全部を学び直す、というのは、一から学ぶよりもさらに楽しかった。なぜなら、すでに流れを知っていたので、より手法を磨き上げ、細部に集中することができたからです。
――そして(ブリストルの)エリック・フレション氏のスタイルは、アラミニッツ(フランス語で「できたて」の意味)で知られていますね。
そうです、ここで料理をアラミニッツでしなくてはならないということを学びました。大切なのは、ゲストのために料理をする、ということ。家で家族に料理をするときは、アラミニッツで料理しますよね。それなのに、レストランではすべてに安全装置がかかっていて、リスクを取りたがらない。なかには、使う3時間前にアスパラガスを茹でておくようなレストランもあると思います。でも実のところ、アスパラガスの調理には2分しかかからない。それならば、安全だから、というだけの理由で、なぜ3時間も前に調理する必要があるのでしょうか。
――しかも、あなたはクラッシックな手法で調理することを好みますね。真空低温調理機を使わずに、素晴らしい肉の火入れをする、その背景にはどんな思いがあるのですか?
シンプルに言えば、そういう調理法が好きだし「料理」が好きだからです。低温調理器の是非はそれぞれが考えればいいことですが、個人的に、ある世代の料理人は、「料理」をするということを学んでいないように思うのです。シェフであろうと料理人であろうと、休みの日に家で家族にちゃんとした料理がつくれなければ、料理人ではないと思います。
――もう少し詳しく教えてください。
単純に、休みの日に、家族になにかおいしいものを料理できるかどうか、ということです。私たちは、一日のうちの15〜16時間をかけてどう料理をするかを学んでいるのに、本当に愛する人に、料理ができないとしたら、なんのためにやっているのですか? レストランはもちろん重要です。でも、もっと大切なことがあります。それは素晴らしい賞を受けることとは違うかもしれません。でも時に、賞はもっとも重要なものではないのです。
私がここ【セザン】で出している料理と同じように、ブリストルの料理は、もっとも複雑な料理ではないと思います。でもすべてのものがきちんと調理されていて、完璧な味わいを持っているのです。
香港とは違う、ここ東京で生み出していく料理とは
 キッチン裏には隠れたシェフズテーブルの個室。レストランの入口を通らずにダイレクトに入室できるのでVIPなどの接待にも
キッチン裏には隠れたシェフズテーブルの個室。レストランの入口を通らずにダイレクトに入室できるのでVIPなどの接待にも
――あなたの料理のスタイルはとても精緻で、テクニカルであり、多くの手作業が行なわれています。どのようにしてこのスタイルを築いたのですか?
細かい手仕事が好きなのは、元警察官で、すべてにおいて妥協をしない、とても緻密な性格の父に育てられたということもあると思います。さらに、いまよりもっと若かった頃は、食材そのものよりも、食材を自分のテクニックを使って、完全に異なるものを生み出し、人を幸せにすることに惹きつけられてきました。しかし、歳をとるにつれて、食材がもっともエキサイティングなものとなりました。早くから料理を始めたことで、それにかなり若くして気づいたのはラッキーだと思います。なかには、手遅れになるまで、気づかないシェフもいると思います。
――その気づきは【セザン】での料理にも影響していきそうですね。
はい。香港では、だれも自分のことを知らなかったから、思い切り技巧的な料理をつくって、認めてもらわなくてはならなかった。でも、いまは信用があり、よりやりたいスタイルができるようになったと感じています。この東京では、寿司屋も懐石も、素晴らしい食材を、とてもシンプルなアイデアと高い調理技術で仕上げている。それと同じことを、フランス料理でできないか、と思っているのです。さらに、日本人は、食に対しての感受性が強い。秋にはマツタケ、というように、特定の季節にしかない食材を心待ちにする文化があるのは、素晴らしいことです。もちろん、西洋料理にも、アスパラガスやトリュフなどがありますが、ここまでではありません。そんな季節感を表現していければと思っています。そしてそれが、ここに来るゲストが望むものだと思うのです。
 店名の【セザン】は、フランス・シャンパーニュ地方の地区で、幼少期にシェフが家族とともに過ごした思い出の地であると同時に、ブランドブランのシャンパンで有名な地区でもある。シェフ自身、「シャンパンを飲むときはいつも特別です」と話す
店名の【セザン】は、フランス・シャンパーニュ地方の地区で、幼少期にシェフが家族とともに過ごした思い出の地であると同時に、ブランドブランのシャンパンで有名な地区でもある。シェフ自身、「シャンパンを飲むときはいつも特別です」と話す
――たとえば、『長野県産軍鶏のポシェ』(通称「酔っ払い鶏」)は、香港の料理文化に根ざしたものでもありますが、日本の料理の文化を、自分の料理に溶け込ませて行きたいと思いますか?
はい、でも注意深くやらないといけません。「東京にやってきた西洋人が、手当たり次第に日本的なものを使う」のではなく、使うのには理由がなければなりません。ゲストはフランス料理を食べにきているからです。酔っ払い鶏は自分の中で腑に落ちる料理です。中国料理の「酔っ払いガニ」に着想を得た料理ではありますが、使うワインはフランスワインですし、フランス風に切りますし、コンソメもフランス料理のものです。この料理が、いつの日かクラシックなフランス料理になってもおかしくないと思っています。
でも、これは香港で5年を過ごすなかで生まれてきた料理です。日本に来て最初の年である今年は、日本の文化の影響を入れすぎないようにしようと考えています。なぜなら、自分がまだ理解し切れていないから。将来的には、どのように取り入れていくかを学べると思います。
――どんな風に食材を理解しようとしているのですか?
そうですね、できる限り外食して、この国のシェフたちがどんな仕事をしているのを知ろうとしています。でもそれをそのまま使うことはありません。「酔っ払い鶏」はどこかでみたアイデアから生まれたものではありません。無理やり生み出したものではなく、自然に「理にかなって」生まれてきたのです。いつか、フランス料理の文脈で捉えられ、かつ日本料理にインスピレーションを受けて生まれた料理ができたらいいと思います。でも、それは目の前にぶら下がっているものではなく、時間をかけて見つけていくものです。
――日本の職人文化はどのように感じていますか?
人の手で機械よりも精密で高品質のものをつくっている日本の職人文化は素晴らしいと思います。そして、その文化が小さな店で、世代を超えて、失われずに受け継がれていることも。そういった職人技に出会うたびに、自分もいい職人になりたい、と感じさせられます。
――最終的には、東京でなにを成し遂げたいと思っていますか?
日本のゲストに愛されるレストランをつくること。それがいちばん大切なことだと思うのです。香港では90%が地元のゲストでした。香港の人たちが私たちのレストランを愛してくれたように、日本の人たちが【セザン】を気に入ってくれて、イギリスの片田舎から出てきた自分ですが、いつか、何千kmも離れた東京が、まるで自分の家になったように感じられるようになることが、私の夢です。
撮影/大鶴 倫宣 取材・文/仲山 今日子 2021.7.28/8.6 取材