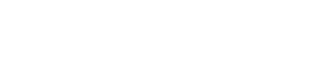アジアのベスト女性シェフ、成功の原風景
 「賞は世界に自分の声を届けるパスポートのようなもの。発信力を上げることで、女性シェフの地位を向上させたい」
「賞は世界に自分の声を届けるパスポートのようなもの。発信力を上げることで、女性シェフの地位を向上させたい」
――今回「Asia's 50 Best Restaurants
2022」での女性シェフ受賞、おめでとうございます。受賞を知らせる瞬間にも立ち会いましたが、ふだん「夢」という言葉を使わない夏子さんが、「夢が叶った」とおっしゃっていたのが印象的でした。
本当にそれくらいうれしかったんです。ずっと目標にしてきたので、それが一つ達成された、という気持ちでいっぱいでした。支えてくれるお客様とうちのスタッフと母の支えがあってなので、感謝しています。
――2020年のベストパティシエに続く快挙。料理の道に進んだきっかけは、中学の調理実習でつくったシュークリームだったとか。でも、これまでの道筋はけっして簡単ではなかったそうですね。
うちは家庭環境が複雑でした。妹に知的障害があって、小さい頃は一緒に暮らしていたんですが、ストレスで父がアルコールに走ってしまって。高校卒業後、【フロリレージュ】のスーシェフをしていたときに、その父が亡くなりました。でも、一日中仕事で死に目にも会えなかったんです。冷たくなった父に会ったとき、いつも励ましてくれていた母にも同じようにしてしまうのではないか、と怖くなって料理の仕事を離れたことがあって。
その後、当時のお客様からリクエストを受けてケーキやお料理をつくっているうちに、自分には料理しかない、と思って店をオープンすることにしました。
――それがいまから9年前の23歳。店を始めたい、と言っても、資金があったわけではないのですよね?
もちろんです。ただ世界観をきちんと表現したかったので、最初からオーナーシェフになろうと考えていました。でも、コネもなく、若くて女性、ということもあって融資がなかなかおりなくて。やっとのことで1000万円を借りたのですが、もし失敗したら母にも迷惑をかけてしまう。だから借りた金額と同じ、1000万円の死亡保険金がおりる生命保険に入って「失敗したら死のう」というつもりで臨みました。融資って結局借金なわけですよね。本当に返せるのだろうか、と毎日怖くて眠れなかったです。
タルトの箱一つつくるにも、信用がなくて、20軒の企業に問い合わせて、実際に仕事を受けてくれたのはたった一軒だけ。
コロナ禍という逆境でも「攻める」という選択を
 2014年の開業当初は、小さなマンションの一室だったが、2019年に現在の場所に移転。モノトーンの外観がスタイリッシュ。
2014年の開業当初は、小さなマンションの一室だったが、2019年に現在の場所に移転。モノトーンの外観がスタイリッシュ。
――その箱を使って実現したのが、有名な薔薇の花の形のマンゴータルトですね。
はい、最初は人が雇えなくて一人でできるのはどんなものだろうと考えたときに「3秒で私がつくったとわかる、マスターピースのようなケーキをつくろう」と思ったんです。マンゴーは、一年中手に入るので季節に関係なくつくれる。どのイベントでも、かならずマンゴータルトをつくって、イメージを定着させたいと考えていました。
――それが成功されて、翌年にはケーキショップ併設のレストランとなるのですよね。今回の受賞につながった部分でもあると思うのですが、ご自身のスタイルをどう表現されますか?
一言でいえば「職人技の表現」だと思います。子どもの頃から、職人技が好きでした。まずは、日本の果物や食材。それがジュエリーのように美しいものだと感じていて、産地に訪れると、年に一度の収穫のための手間が見えて、生産者は職人だと実感するのです。
それを、料理の職人である私が、自分の技でさらに輝かせる。店内のインテリアは、アーティストとのコラボで定期的に変えますが、アートも究極の手仕事だと思います。職人技でつくられた食材を、同じく職人技でつくられたアートの中で食べていただく。その架け橋として、職人である私と【été】というレストランがある。そんなイメージです。
日本では職人の価値が低く見られすぎている。世界の舞台で光を当てることで、後継者不足などの問題の解消につなげたい、とも思っています。
 コースの最後、たくさんの薔薇の生花と共に、ガラスのドームをかぶせてジュエリーのように提供されるマンゴータルト。
コースの最後、たくさんの薔薇の生花と共に、ガラスのドームをかぶせてジュエリーのように提供されるマンゴータルト。
――確かに、時期ごとに変わるアートの展示も【été】に来る楽しみの一つですよね。職人技と職人技をつなぐ以外に、アートとのコラボに重要性を感じているようにも見てとれます。
アートとのコラボをしていると同業者からは「チャラチャラしてる」と思われたりしますが、私自身は、食を愛好家だけのクローズドな世界にしてしまうと、業界の未来をつくっていけないと思っています。後継者不足は料理業界も同じです。
たとえば、野球を知らない私でさえもメジャーリーグの存在は知っている。そこまでの認知度になれば、しぜんと目指す人は増えるわけです。アートとのコラボをきっかけに私を知って、若い子が興味を持ってくれたらうれしいし、職人技の世界への興味の入り口にもなりたい。背中を見る子たちを育てないといけないと思うので、いまはそこも力を入れています。
――【été】は一日一組、6席だけのレストラン、テーマは「世界でただ一つの、小さな楽園」。
コロナ禍では、誰とどんな時間を過ごすかを見直す機会になりましたよね。うちのように一日一組のレストランだと、一緒に行く方を慎重に選ばれるし、一生に一度あるかないかの勝負のときに使っていただくこともあります。店全体が自分の表現のスペースでもあり、かつお客様が手に取るもの、目にするものすべてはおもてなしの要素でもあります。
提供する料理にはすべてストーリーがあって、たとえば私が海外でコラボレーションしたときに相手のシェフからいただいたインスピレーションだとか、あとはお客様から「あの国を旅行したときの料理が忘れられない」とか、何気ない会話でいただいた言葉を汲み取ってお料理をつくる。そういうことを大事にしています。
その日に来店するお客様で名前を知らない方はいないし、お客様のストーリーをスタッフ全員で共有しています。私にとってラグジュアリーは、一皿にかける思いをお客様と一緒につくり上げていくっていうことだと思いますね。
 石工も後継者不足の業界。花崗岩のオブジェを購入してアーティストを支え、伝統技術の「サステナブル」も追求する。
石工も後継者不足の業界。花崗岩のオブジェを購入してアーティストを支え、伝統技術の「サステナブル」も追求する。
コロナ禍という逆境でも「攻める」という選択を
 「ファッションメゾンのコレクションのように、非現実の世界観を演出したい」お客様の目にふれるもの全てにこだわる。
「ファッションメゾンのコレクションのように、非現実の世界観を演出したい」お客様の目にふれるもの全てにこだわる。
――2022年2月には中東・北アフリカの「50 Best Restaurants」の授賞式に合わせてアラブ首長国連邦・アブダビ
でポップアップを行うなど、海外での活動も続けていらっしゃいます。
コロナ禍で海外に行く人は激減したと思いますが、これまで仕事をしてきたアーティストの方とかってコロナのときでも攻めているんですよね。仲良くしていただいている「AMBUSH」のデザイナー・YOON(ユン)さんも、ミラノコレクションでショーをやるために、何回も海外に行かれている。それを見て、「自分たちも攻めないと」って思ったんです。もちろん、それもお客様の支えがあってこそです。
実際、店を閉めるし、隔離もあるしで資金的には大変なんですけど、でも自分たちが成長しないといけないので。リスクを取っても、思い通りに行かないこともありますが、海外に出ていかなかったら逆境すら経験できない。まだまだ仕掛けていきますし、スタッフにも違う世界を見せたい。それをまたお客様に還元できるじゃないですか。
――現地では世界の女性シェフたちとのコミュニケーションを図れたようですよね。
日本ではとくに女性シェフが少ないので、海外の最前線で勝負する女性シェフに会えたのは有意義でした。
いま私がフォーカスされているのは、“女性シェフ”というのもあると思います。女性シェフが少ないからフォーカスして、男性シェフとのバランスを均等にしよう、という動きです。それもいいことだと思うのですが、将来的には性別へのフォーカス自体がなくなればいいと思っています。女性、男性、若い子も料理の世界でみんなが切磋琢磨している。私が生きてるうちに、そんな世界にしたいです。
――成功するための覚悟のようなものを強く持っていらっしゃると思うのですけれど、その原点ってなんなんでしょうか?
家庭の状況もあって、家族を支えないといけない、ということ。あとは、同じことをやる人がいないから、自分がやるしかないという使命感。
【été】は、特別な日に来ていただく場所です。毎日が勝負で、この勝負を逃したら死ぬと思って仕事をしろって、いつも自分と対話しながら鼓舞しています。リスペクトする人もいるし、刺激を受ける人も大勢いますが、結局自分との戦いなので。
サステナブルな飲食業界の未来をつくる
 「起業したての頃は、眠れない日が続いて苦労したけれど、客観視したら『あ、この経験って世の中の役に立つな』と」
「起業したての頃は、眠れない日が続いて苦労したけれど、客観視したら『あ、この経験って世の中の役に立つな』と」
――ご自身をすごく客観視されていますよね。苦労された経験を若い世代の糧にしたいと、母校で教壇に立っているとお聞きしました。
オープンのときにスタッフを雇いたくて、歳上の人は雇えないだろうと思ったので母校に行ったのがきっかけです。その時、独立するときに必要なことを学校で教わってないことに気づいたんです。お店を出す段になって、一番に直面した問題が資金でした。それを解決するには事業計画書をつくって銀行にプレゼンしないといけない。私のように、料理しかやってこなかった、当時20代前半の私にとっては、地獄のように大変でした。
学校では和洋中の料理を全部習うのに、お店を出すうえで最初に直面することを教えてくれない。それができるのは私しかいないと思ったし、若い女性ということで苦労もしたけど、逆に生徒に近い視点で話ができるし、私の経験はかなり使えるなと、自分を俯瞰して利用価値を見出したわけです。起業の苦労とか、おいしいものをつくるだけではお客様が来ない、どうやって集客をするのかっていうストーリーを教えたいと考えました。
 焼きたてを目の前で切り分ける、シグネチャーのブリオッシュ。バターが香る湯気もごちそうの一部だ。
焼きたてを目の前で切り分ける、シグネチャーのブリオッシュ。バターが香る湯気もごちそうの一部だ。
――食の世界で関心が高まっているサステナブルについても、教えているそうですね。
日本だと、高校生ではまだサステナブルって現実感がなかったりするようですが、世界のトップシェフの間では知っていて当然のことなんです。もともと【été】では取り組んでいましたが、一日一組の規模だと社会的なインパクトが大きくない。
でも、学校だったら規模も大きいし、若い世代の「当たり前」にすれば、サステナブルな未来がつくれる。この前、学校を説得して野菜の切れ端などを液肥にするコンポストを入れてもらいました。実習や【été】で出た生ゴミとかを液肥にして、学校が借りている畑で使っています。畑の野菜を収穫してまた実習で使ったり、【été】でも出すというひとつのサイクルのようにして、農から食へ、というのを実践しています。
――サステナブルも、いろいろな意味でのサステナブルがあると思います。未来の食の世界がこうあって欲しい、という理想のようなものはありますか?
次はアジアを超えて、世界のベスト女性シェフ賞を目指したいと思っています。それが取れたら飲食業界のサステナブルに対して、もっと影響力が持てるようになるし、私のように辛い思いをする人たちが出ないように、プラットフォームもつくりたいと思っています。たとえば、若い子にどんどんチャンスが与えられるとか、お店と子育ての両立が当たり前にできる世界をつくるとか。
あとは職人の世界へのお金の循環もよくしたいと思っています。【été】の料理やプロダクトは「なんでこんなに高いんだ」ともよくいわれるんですけど、そうしないと生産者やスタッフに還元できないんです。私たちが4〜5万円のお料理を出しているのにスタッフがそのレベルの料理を食べてなかったり、世界を旅しているお客様が来るのに私やスタッフが世界を知らないのではいけない。自分たちのプロダクトにアートの価値をつけることで、それもお客様に還元して、喜んでもらえればと思っています。
未来を変える覚悟
 分厚いフィユタージュでできた『ホオズキとキャビアのミルフィーユ』だが、ナイフを入れると、小気味よくさっくりと割れる。
分厚いフィユタージュでできた『ホオズキとキャビアのミルフィーユ』だが、ナイフを入れると、小気味よくさっくりと割れる。
――先ほど「自分との戦い」とおっしゃっていましたが、自分自身のためにリラックスする時間はあったりしますか?
自分の中では、庄司夏子とは別に【été】をやっているもう一人の自分がいて、「エテ子さん」って呼んでいます。でも最近は、「エテ子さん」じゃないほうの“個”の自分がどんどんいなくなっていて。最終的に【été】の庄司夏子でしかいられないな、って思う気持ちがあります。いまは、お店以外のことに興味が湧かない。100%。目標とかスタッフとか、お店以外のことに脳みそを1%も使いたくないんです。
――いまの状態の中で、幸せだと感じるときはありますか?
学校で生徒にも「世界を変えたいと思うなら、友達や恋人と過ごすようなふつうの幸せな時間が人並みにあると思うなよ」とも伝えていますし、私自身がそうやって進んできました。
もちろん同級生と会えないことに寂しさもあります。結婚、出産、いろいろ報告は聞くんですが、友達に会う時間を削って、いまは前進に使っています。「後で倍にして返すから、結果を出してお返しするから、待ってて」って言っています。
いちばん幸せなのは、がむしゃらに全身全霊をつくして仕事をした後に、お客様の感謝が返ってくる。そういう、お客様とのコミュニケーションの部分です。辛くて死にそうになる気持ちもありますけど、この幸せには変えられないなと思います。
――本当に、強い覚悟をお持ちなんですね。これからの庄司夏子が目指すことはなんですか?
自分もお店もまだ発展途上だと思っているので、いまは可能性しかない。だからこそ、一日でも若いうちに突き進んで行きたいです。若いっていうだけであれだけ辛い思いをしてきたのに、今度は一日一日歳を取るという現実を見る部分もあります。物覚えが悪くなったり、体にガタがきたり、ヘルニアの手術をしたり……無敵じゃないな、と。でも、闘志がみなぎるいま1分1秒を無駄にしたくないと思っているので。
つねに時間がないって思ってます。頭も体も動くうちに、一日一日前進したいです、切実に。
撮影/清水伸彦 取材・文/仲山 今日子 2022.2.25 取材